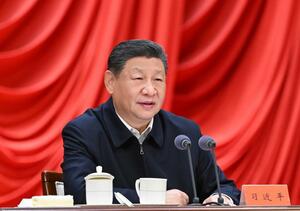(英エコノミスト誌 2023年10月7日号)
 安全保障も考えない無暗な自由貿易の時代は終わりを告げたようだ
安全保障も考えない無暗な自由貿易の時代は終わりを告げたようだ
各国政府が世界を豊かにした原則を投げ捨てている。
時折、例えば戦争や革命の時には、根本的な変化が華々しく姿を現す。多くの場合、そうした変化はこっそり忍び寄ってくる。
本誌エコノミストが「homeland economics(ホームランド経済学、内向き経済主義)」と名付けたイデオロギー、すなわち野心的な国家が自国の産業に多額の補助金を出し、介入も大いに行う保護貿易主義のイデオロギーは後者のパターンだ。
脆弱なサプライチェーン(供給網)、安全保障上の脅威の高まり、エネルギー転換、そして生活費危機はそれぞれに政府の対応を求めたし、それも無理からぬことだった。
だが、これらをひとまとめにすれば、開かれた市場と役割を限定した政府という想定がどれほど組織的に蔑ろにされてきたかが明らかになる。
自由主義を唱えればバカにされる風潮
本誌にとってこれは憂慮すべきトレンドだ。
本誌が1843年に創刊された理由のうち特に重要だったのが、自由貿易と政府の役割の限定を支持するキャンペーンを展開することだったからだ。
このような古典的自由主義の価値観は昨今では不人気なうえ、政治の議論の場でますます顧みられなくなっている。
8年足らず前には、米国のバラク・オバマ大統領(当時)が環太平洋諸国と大型の貿易協定を結ぼうとしていた。
今では、米ワシントンで自由貿易を主張しようものなら、どうしようもない世間知らずだとバカにされるのがオチだ。
新興国で同じことをすれば、自分たちが物事を一番よく理解していると西側諸国が思い込んでいた時代からやって来た新植民地主義者だというレッテルを貼られるだろう。
本誌は今週号の特集で、内向き経済主義は結局、失望をもたらすと論じている。
このイデオロギーは何がいけなかったのかを見誤っており、果たすことのできない責任を国家に負わせ、社会と技術が急激に変化しているこの時代のかじ取りに失敗する。
良い知らせがあるとすれば、それは内向き経済主義がいずれ自壊するということだ。