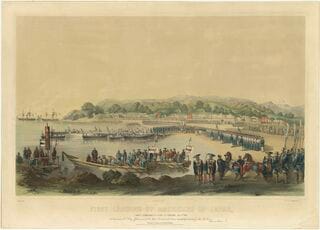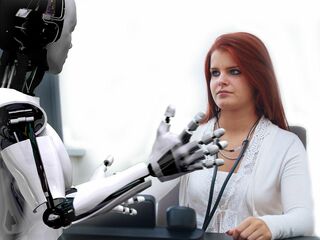水運業という未知の世界に飛び込むにあたっては、相当の葛藤と覚悟を迫られたに違いないが、「70歳を超えた父1人では、現地との往復も書類の作成も限界がありますから」「素人だったのがかえって良かったのでしょう」と、どこまでも爽やかだ。
かくして始まった武司氏の挑戦は、さぞ、人との縁に満ちていたはずだ。
マンダレー港のハプニングがあった後でさえ、武司氏と笑顔でその後の段取りについて打ち合わせるミャンマー人スタッフたちからは、営業や通訳、ドライバーといった役割を超えた「同志」としての連帯感と、「物流の改善を通じて祖国の発展に貢献したい」という誇りが伝わってくる。
何か問題が起きても、怒ったり衝突したりせず、相手にきちんと伝えることを重視する武司氏の自然体で鷹揚な人柄があったからこそ、こんなチームが結成されたに違いない――。笑い合う彼らを見ながら、ふとそんなことを考えた。
水面に輝く挑戦
 企業セミナーであいさつをする宮本武司氏
企業セミナーであいさつをする宮本武司氏
7月下旬、武司氏は判司氏とともに、ヤンゴン市内のホテルで日緬両国の企業関係者ら約140人を対象にセミナーを開き、2回にわたる実証実験の結果を報告した。
さらに、「コンテナ輸送の事業化に向けて今後もこの国で挑戦し続けたい」との決意も明らかにした。
もちろん、課題はある。第1に、ライバル企業の存在だ。内陸水運の会社は国内に400~500社あり、棲み分けが必要なのだ。そこで重要になるのが、価格競争に陥らないこと。
「例えて言うなら、ただサーカスを見せるのではなく、シルクドソレイユのように、舞台性やテーマ性、ストーリー性を持たせることで、コストが高くても他が追随できない新たな価値を提供し、同じ市場で競わなくてもすむ存在になる」というのが、武司氏の戦略だ。
水運に関わる企業は多くても、コンテナを載せて航行できるバージ船は、今回、この国で建造した台船ただ1隻だ。さらに、この台船は、コンテナ専用船としても、重量物専用船としても活用できる上、将来的にはコンテナを吊り上げるクレーンも搭載できるよう、設計段階から考えられている。
「自分たちで価格を設定し、新しい市場を開拓していけるだけの付加価値は十分出せる」と武司氏は強気だ。
第2に、規制のハードルも高い。よく知られているように、日本をはじめ、多くの国が「内陸水運は自国船に限る」という「カボタージュ規制」を設けている。ここミャンマーも、例外ではない。
内陸水運公社(IWT)との合弁企業であればその限りではないとはいえ、新規参入は決して容易ではない中、「どうすればビジネスになるのか」、模索が続く。
第3に、人材育成の必要性だ。
マンダレー港でのハプニングからも、「人の意識を変えないと行動は変わらない」ことを痛感している武司氏。今後は、日本の水運業のやり方を導入することで賃金が上昇し、労働条件も良くなることを伝えた上で、「日本の企業人と意思疎通でき、同じ目標に向かって進んでいける人材」を育成しようとしている。
ただ船を作ってコンテナを運ぶだけでなく、数々の課題の解決に挑む宮本さん親子。その挑戦は、今、ようやく曙光が見えてきた段階だが、彼らの背中を見ていると、近い将来、イラワジ川の岸辺にバージ船が停泊し、クレーンでコンテナが積み下ろしされている景色があちこちで見られるようになるかもしれないと思えてくる。
「ゼロから一を作る協力こそがこの国の発展につながり、われわれの勉強にもなる」――。果敢に挑み続ける瀬戸内の企業魂が、大河の水面に輝いている。
(つづく)