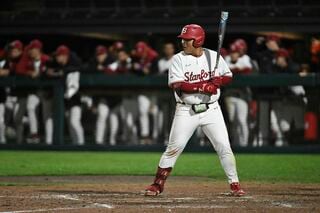トム・ハンクスさんとリタ・ウィルソンさん夫妻(2014年1月18日撮影、資料写真)〔AFPBB News〕
スティーブン・スピルバーグ監督の最新作、『ブリッジ・オブ・スパイ』(2015)が劇場公開されている。コーエン兄弟が脚本を手がけ、主演はトム・ハンクス。
アカデミー賞の常連が描く冷戦時代の「スパイ交換」の実話は、先日発表されたノミネーションでも、作品賞、脚本賞、助演男優賞、作曲賞、美術賞候補となっている。
映画は1957年のニューヨークから始まる。ハンクス演じる主人公は、ソ連のスパイ容疑で捕まった男の国選弁護人ドノヴァン。かつてニュルンベルク裁判で検察官を務め、いまは保険を専門としている。
勝ち目はなく、「敵」を弁護すれば、自身のみならず家族までもが国民の嫌悪の対象となる。それでも、「どんな人間にも、公平な裁判を受ける権利がある」と弁護を引き受ける。
スピルバーグが描く不寛容
そんな裁判を行うのには、「米国は、敵のスパイでも、公正な裁判をする」と世界に見せる意図があった。
「自由の国」「正義の国」であるはずの米国に塗られた近年の「不寛容」のイメージを払拭する意味があったのだ。だから、それは「形式」に過ぎない。しかし、ドノヴァンは本気で弁護した。
そんな当時の「不寛容」な世相を、スピルバーグは、同じ1957年が舞台の『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』(2008)で、すでに描いている。
相棒がカネ目当てにソ連側に寝返ったため、FBIの捜査を受けたインディ・ジョーンズは、反共の空気が強い世でトラブルを恐れる大学から、無期限停職とされてしまう。米国の現実に失望し、インディは外国に向かうが・・・と始まるのである。
第2次世界大戦終戦後間もなく、朝鮮戦争を引き起こした東西対立は、米国国内でも、「赤狩り」という形で社会を変容させていた。
共産主義を強く排斥するマッカーシズムの世となった「自由な民主主義国家」米国の「魔女狩り」のごとき現実を、劇作家アーサー・ミラーは「るつぼ」で描き、1953年、上演。