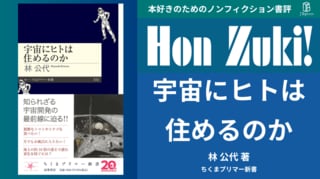日本の代表的な蒸留酒「焼酎」の歴史と現在を、前後篇で追いかけている。前篇では、焼酎がシャム(タイ)から琉球(沖縄)経由で薩摩(鹿児島)に入ってきたという有力な説を紹介した。そして、芋焼酎が飲まれていた鹿児島で、2次仕込法や白麹菌を使うという、焼酎づくりの革新が起きたことを紹介した。
後篇では、その後の焼酎づくりの発展を見ていきたい。1970年代に、第1次焼酎ブームをつくり出した宝酒造に取材をし、現代の焼酎づくりの技術の広がりをたずねた。美味い焼酎への追求は、進化・発展し続けているようだ。
焼酎づくりに“新式”誕生
明治時代後期、鹿児島の人々はいまに続く焼酎づくりの方法を築いた。その一方で、明治から大正にかけての時代、これとは別に日本人は「新式焼酎」と呼ばれる焼酎のつくり方を打ち立てた。
新式焼酎とは、糖蜜や穀類などを主原料として、それを発酵させ、さらに「連続式蒸留機」で蒸留を何度も繰り返し、そうしてできたアルコールを水で割ってつくる焼酎のことである。蒸留を繰り返すことで、不純物を取り除き、純度の高いアルコールをつくることができる。
いま、焼酎のラベルを見ると「甲類」「乙類」といった表示がある。このうち新式焼酎の流れを受け継ぐのが甲類だ。一方、乙類は、前篇で紹介したような、新式焼酎が生まれる前からあった従来法によるもので「本格焼酎」とも呼ばれている。
新式焼酎の原点は、1899(明治32)年、実業家の神谷伝兵衛(1856~1922)がドイツから輸入した連続式蒸留機であるという。ちなみに神谷は、東京・浅草にいまもある「神谷バー」の経営者だった。