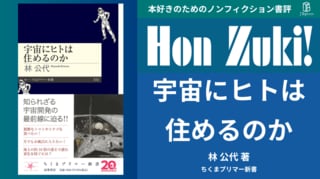ニッケイ新聞 2012年7月12日
永住の 緑天国 五十五年―。
アマゾナス州中流の町、パリンチンスで俳句に親しむ戸口久子さん(78、宮崎、旧姓恒松)は、同地に住む唯一の一世だ。移住50年目を迎えた2005年、句集『アマゾンに生く』を、2010年2月に同題の第二句集(79頁、星野瞳編)を刊行した。
「自分が忘れないようにと思って・・・」。移住当時から現在に至るまでを振り返りながら作句に励み、『ブラジル俳文学会』に投句する日々だ。
「ここは交通の便が悪いので、届いてないのか載らないこともあるんですね」と静かに笑う。
同地に住み始めたのは1972年。子弟の教育を考え、転住した翌年に開店した食料品店(現在はスーパー)のレジ係として今も出勤する。25人の従業員を抱えるが、「ちゃんと見ないといけないから」と家族で仕事に精を出す。
「日本にいたら何が起こるかわからない」―。約10年もの間戦地で過ごし、帰還した父。戦争のないブラジルへの移住を望んだ。
「ワニや豹のいるようなところに行くのか?」と周囲に心配され、おじにも強く引き止められたが「戦後で仕事はなく、家も焼けた。両親が行く所はどこでもついていって頑張りたい」と1954年5月、「あふりか丸」で神戸港を出港。20歳だった。
7月にべレンに入港。アマゾンを遡行する船に乗って目的地パラー州モンテ・アレグレへ。20家族での入植地生活が始まった。耕地の指導員と家長らが原始林に分け入って良質の土壌を探し出し、各家族に土地が割り振られた。
山の下刈りには、久子さんも駆り出された。生まれて初めて斧を手にし、「(滞在した)2年6カ月で男の手みたいになった」。
食糧と生活必需品の購入には定期便のトラックで50キロ先の町まで出かけて行き、日曜日は入植者が設立した組合でも働いた。「二十歳の若さ故、何も辛いとは思わなかったが、父母と姉弟揃って頑張りました」(同著の「回想」より)。