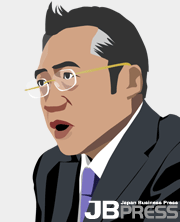既に、旧聞に属する話題だが、東証株価指数(TOPIX)は大発会から6営業日連続で上昇した。バブルが崩壊した1990年以降、TOPIXの年初からの連騰記録は94年5日間が最高だったことを考えると、いかに2010年が勢いのあるスタートだったかが分かる。その後も東京市場の騰勢は衰えず、日経平均株価は15日の取引時間中に1万982円10銭まで上昇、1万1000円の大台に迫った。
東証株価指数は大発会から6連騰。東京市場は明るいスタートを切った〔AFPBB News〕
この上昇局面での主役は明らかに外国人投資家だった。
外国人投資家の動向を理解するためには、東証の「投資主体別売買動向」と、財務省の「対内対外証券投資」の2つの統計が便利だ。共に外国人による日本株の売買を集計したものだが、財務省統計には、取引所を経由しない公募株の取得や、市場外取引も含まれるのが特徴だ。
2009年10-12月期、上場企業は総額5兆円規模の公募増資を行った。最近は増資の5割程度を海外向けとすることが多く、こうした局面では、財務省統計の方が実態を正確につかみやすい。
1月第1週の対内証券投資は7351億円の買い越しだった。2001年からの週間ベースで、過去5番目となる巨額の買い越しだ。第2週も6121億円と高水準の買い越しを続けた。つい2~3カ月前まで、外国人が東京市場に見向きもしなかったことがウソのようだか、一体、何が彼らの行動を変えさせたのだろうか?
菅財務相の為替口先介入が意外な好材料に
 外国人投資家の目にはデフレファイターに映った?
外国人投資家の目にはデフレファイターに映った?
外国人投資家の多くが指摘するのは、第1に、日銀の方針転換だ。2009年12月1日、日銀は緊急に金融政策決定会合を開催し、「新型」のオペで10兆円を供給することを決めた。日本の市場関係者からの評価はイマイチだったが、外国人はこれを素直に好感した。
2つ目は、新年早々に就任した菅直人財務相の為替相場への口先介入だ。就任会見での円安誘導発言には、鳩山由紀夫首相も「政府は為替に言及すべきではない」と苦言を呈するなど、政府内でも波紋を呼んだ。
しかし、外国人投資家は、この2つの事象を組み合わせて「政府・日銀は連携してデフレに対峙しようとしている」と受け止めたようだ。