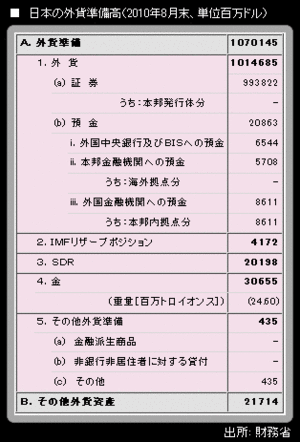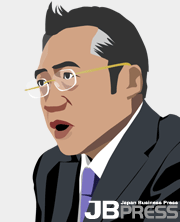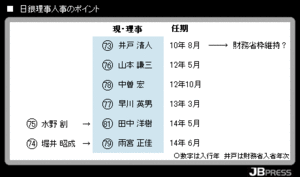山口広秀副総裁を右腕に得て、本格始動した日銀の白川方明体制。いきなり利下げに追い込まれ、金融政策運営は相変わらず冴えない。対照的に、金融調節(オペレーション)の技術は世界最高水準を誇り、最近では独特の資金吸収手段である売出手形(売手=うりて)を英国やスイスの中央銀行が模倣するなど、日銀のオペ手法は「世界標準」になりそうな雲行きだ。
英中銀、日銀オペを教科書に〔AFPBB News〕
金融危機の下で各国の中銀が潤沢な資金を供給する中、なぜ対極にある資金吸収の手段を導入するのか。それは後述するとして、まずは日銀の誇る金融調節のレベルについて解説したい。
あまり知られていないが、日銀のオペ技術の高さは中央銀行界ではかねて定評がある。インターバンク市場での銀行券と財政資金による資金変動幅が数兆円規模に上るのに、日銀は政策金利(無担保コール翌日物)をほとんどブレることなく、「精密誘導」できるからだ。資金変動幅が日本より小さくても金利安定に苦労する他国の中央銀行からは、日銀の調節が「神の手」に見えるらしい。
しかも、日銀は1990年代後半に深刻な金融危機に直面し、資金を潤沢供給して難局を乗り切った経験がある。さらに、2001年には実験的な金融政策である量的緩和に踏み切り、当座預金残高を30兆円前後まで積み上げる芸当まで見せつけた。
冷笑から称賛に転じた欧米
もっとも、日銀の「神技調節」が真に称賛を得ていた、というわけではない。
インターバンクの資金変動が大きいのは財政膨張が主因だし、金融危機はバブル発生のツケが回ってきたもの。さらに、量的緩和はデフレに陥った代償でもある。つまり、経済運営の失敗が調節技術の高度化を促した側面があり、好調な経済を続けていた欧米の中央銀行は「曲芸」のように見ていた。
実際、日銀の調節体系はやや醜悪と言わざるを得ない。一般的に、調節手段はシンプルなほど美しい。少ない手段で必要な金融調節が可能ならば、それだけ効率が高く、機能美に優れている。この点、日銀の供給・吸収手段の数は欧米(2~3本)の2倍以上もあり、多機能だが格好悪い。
手段の中で最もキワモノなのが、冒頭で紹介した「売手」。これは、中央銀行が自ら負債(手形)を発行し、市中から資金を吸収するもの。いつでも発行できるので機動性は高いが、中央銀行が国債まがいの負債を乱発する不健全なイメージがあり、日銀関係者も「スマートさを欠く手段ではある」と恥ずかしそうに認める。