問 米国のシリコンバレーではテスラ・モーターズという電気自動車メーカーが生まれ、大変な人気のようです。まさに先生が言われる「秋葉原で自動車が作られる」ことを実証して見せたようなものですね。日本でも遠からずその時代が来ると見ているわけですね。
妹尾 そうです。日本はハイブリッド車で世界を完全にリードしていると誇るのはいいでしょう。確かに性能も素晴らしい。でも、そのことが電気自動車の時代を一気に引き寄せていることをきちんと理解し、次の手を打たなければなりません。しかし、私の見る限り、どうもその手を打っているようには見えないのです。
世界に目を向けると、ハイブリッドは日本車メーカーに任せて、その次で覇権を取ろうという動きが鮮明になっています。ドイツの部品メーカー、ボッシュは電気自動車の時代をにらんで、様々な部品の標準化を進めています。ボッシュが標準化で先を行ってしまえば、日本メーカーはそれに倣わなければならなくなります。
タタ・モーターズの本当の野望を見抜いているか
また、今年インドのタタ・モーターズが20万円で買える自動車を発売して世界を驚かせました。皆、20万円の価格にびっくりしていますが、価格に驚いているだけではいけません。タタは電気自動車の時代の覇権を取ろうとしているのです。
電気自動車の時代は、パソコンや家電製品と同様に、部品をモジュール化・標準化してコストを下げ組み立てを容易にすることが競争力のカギを握ります。タタは、「ナノ」という20万円の乗用車で、次世代技術の実証実験をしていると見るべきなのです。「あんなクルマに先進国の人間は乗らないさ」などと侮っていては、足をすくわれてしまいます。
問 自動車産業は完成車メーカーが頂上に立ち、部品メーカーがそれを二重三重に支えるピラミッド型の産業構造をしています。その堅牢なピラミッド構造が日本車メーカーの強さだったわけですが、それが根底から崩れてしまうわけですね。そうなると、開発のあり方も大きく変わってきますね。自社完結型から様々なリソースを組み合わせるような形になるのでしょうか。
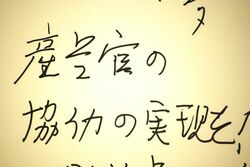 産学官の緻密な連携が最も大切
産学官の緻密な連携が最も大切
妹尾 オープンイノベーションという言葉をご存じでしょう。技術をどんどん開放して自社だけでなく多くの企業を巻き込んで新しい産業や市場を一気に拡大させる考え方です。自動車産業もそのような形に変わってくると思います。しかし、これには注意が必要です。世界がそのように変わり始めたから、日本もその流れに遅れてはいけないとばかりに盲目的に取り入れるのは危険です。
オープンイノベーションは確かに面白い考え方ですし、成功すればメリットも計り知れません。しかし、これには周到な準備と戦略が不可欠です。
闇雲な開放は途上国を利するだけ
技術を開放すれば、とりわけ発展途上国の技術水準を上げ、コストの安い部品や製品が供給されるようになるので、新しい市場が生まれたり市場が活性化するでしょう。しかし、その時に日本や日本の企業はどのような恩恵を受けるのでしょうか。
その点の戦略をしっかり組み立てることが必要です。闇雲に何でもオープンだとやってしまえば、何のことはない、他人を利するだけで終わってしまい、自分には何も残らない危険性があります。日本は技術大国です。オープンイノベーションによって確かに新たな発展を手にできるチャンスはあります。しかし、戦略を誤ると、技術をタダで開放しただけに終わってしまいます。
日本は国の政策担当者も企業もそういう青写真をしっかり描くことが意外に苦手です。ではどのような青写真を描けばいいのか。次は時代ごとのイノベーションのあり方を検証する形で見てみたいと思います。(明日につづく)














