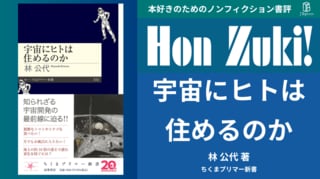生成AIの開発コストの低減に成功したDeepSeek(写真:JarTee/shutterstock)
生成AIの開発コストの低減に成功したDeepSeek(写真:JarTee/shutterstock)
ChatGPTを筆頭に生成AI市場は熾烈な競争の最中にある。その市場に新たな風を吹き込んだのが、中国発のスタートアップが生み出したDeepSeekだ。高精度かつ低コストの学習技術で市場に衝撃を与えたこの生成AIは、果たして覇権を握る存在となるのか。
DeepSeekの革新の背景と今後の可能性について『DeepSeek革命―オープンソースAIが世界を変える―』(池田書店)を上梓した長野陸氏(株式会社piland 代表取締役社長)に話を聞いた。
──2025年1月20日、中国のAIスタートアップ企業、DeepSeek社が生成AIツール「DeepSeek R1」をリリースし、大きな話題となりました。DeepSeekの特徴の一つとして、従来の生成AIと比較して開発コストが格段に安価である点が挙げられます。どのようにして開発コストを低減したのでしょうか。
長野:ChatGPTをはじめとする従来の生成AIは、膨大な量のデータを学習させることによってその精度を担保してきました。
一方、DeepSeekではAIモデルを設計するにあたり、要点をかいつまんで学習させる手法を採用しました。このようなアルゴリズムの工夫により、開発コストの低減に成功したと考えられます。
ヒトの学習に例えるのであれば、従来の生成AIは教科書の1ページ目から100ページ目まで隅々に目を通して、すべての内容を完璧に記憶します。少し効率の悪い勉強法かもしれません。
それに対して、DeepSeekは1ページ目、2ページ目に目を通し、3ページ目も似たような内容であればそこをスキップして4ページ目に進みます。要点を押さえ、重要な部分を重点的に学習しているのです。
そのため、DeepSeekは効率的に広範囲な知識を獲得できます。このアルゴリズムの一工夫が、DeepSeekの開発コストの低減と性能の高さを実現しているのです。
──その学習方法によって予測精度が低下することはないのですか。
長野:逆に精度が高くなることが期待されます。従来の生成AIのように全データを網羅的に学習する場合、似通ったデータも学習するため、かえって誤りが生じやすくなると言われています。
DeepSeekは、必要な情報を効率的に抽出することで精度の高さを維持し、さらには推論速度の向上にも成功しています。
──特殊な学習アルゴリズムは、DeepSeek独自の技術なのですか。