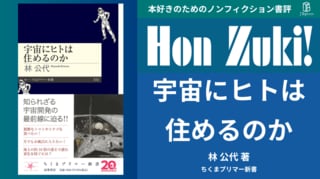経済財政諮問会議で発言する石破首相。実質賃金の1%程度の継続的な上昇で経済成長を目指すという(写真:共同通信社)
経済財政諮問会議で発言する石破首相。実質賃金の1%程度の継続的な上昇で経済成長を目指すという(写真:共同通信社)
「賃上げ率5%」の見出しが並ぶ一方で、物価上昇に追いつかない実質賃金。一方で、この30年で日本の生産性は約30%向上しているという。生産性は上がっているのに、なぜ賃金は増えないのか。
企業利益が従業員に還元されない構造、日本企業の海外志向の誤算、今後のイノベーションのあり方について『日本経済の死角──収奪的システムを解き明かす』(筑摩書房)を上梓した河野龍太郎氏(BNPパリバ証券チーフエコノミスト/東京大学先端科学技術研究センター客員教授)に話を聞いた。(聞き手:関瑶子、ライター&ビデオクリエイター)
──本書のサブタイトルにある「収奪的」という言葉について教えてください。
河野龍太郎氏(以下、河野):「収奪的」とは、他者の労力や資源を一方的に奪う行為を指します。書籍中では、企業が利益を上げても働く人に還元されない構造をこの言葉で表現しました。
日本では過去30年で、時間当たり生産性が約30%向上しているにもかかわらず、時間当たり実質賃金はほぼ横ばいです。米国では生産性が50%増加したのに対して実質賃金は30%上昇しています。
けれども、米国並みに生産性を上げなければ、実質賃金は上がらないのかというとそういうわけではない。ドイツは約25%の生産性上昇に対して15%弱、フランスは約20%の生産性上昇に対し20%弱、実質賃金が増加しています。
このような点から、日本の社会は収奪的ではないかと私は考えています。
──日本は、なぜそのようなシステムに陥ってしまったのでしょうか。
河野:景気が悪化すると、米国では倒産を避けるため、当然のように雇用リストラを行います。一方、日本では大企業を中心に長期雇用制が根付いており、不況でも日本の大企業は従業員の雇用を守ることを優先させてきました。
1990年代末まで、日本にはメインバンク制という制度がありました。メインバンク制とは、企業が複数の銀行と取引するなかで、主力銀行が融資だけでなく、経営上の助言、経営が傾いたときには再建支援や追加融資を行ってくれる慣行のことです。
こうしたメインバンク制の存在が、長期雇用を前提とする企業の安定経営を支えていました。
ところが、1990年代末の銀行危機などを背景に、メインバンク制は事実上機能しなくなりました。その結果、大企業は外部支援に頼れなくなり、長期雇用制を維持するために自らの体力を高めるべく自己資本の強化を迫られるようになったのです。
自己資本を積み上げるには、まず利益を確保する必要があります。そのため企業は二つの手段をとりました。一つが正社員の賃上げ(ベースアップ)の凍結で、もう一つが労働力の一部を非正規雇用に切り替える動きです。
長期雇用を前提とした正社員の人件費は固定費ですが、非正規雇用であれば変動費として扱えます。こうして企業は、固定費の一部を変動費に置き換えることで、収益を高めようとしました。
この構造変化こそが、日本企業に根づいた収奪的な雇用システムの背景にあります。
──ここ数年、日本はようやくベアが復活している状態です。にもかかわらず、河野さんは今後も実質ゼロベアが続くのではないかと危惧していました。