AIを活用して俳句を作る、これが「邪道」ではなく「正統」な理由
正岡子規も切望した19世紀最新技術「辞書」の電子化、金子兜太も苦吟した推敲の本質
2025.6.4(水)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
連載の次の記事
違法風俗店経営の「国立大学准教授」とSTEAM教育の終焉

あわせてお読みください

大阪万博で大量発生中のユスリカ対策、実は殺虫剤より効果的な小魚
1950年代に八丈小島で奇病「バク」を根絶したそのパワー
伊東 乾

トランプ政権のハーバード攻撃は日本復活の絶好のチャンス、優秀な留学生受け入れ競争に負けるな
「コスモポリタン」だけがチャンスを生かすことができる
伊東 乾

殺虫剤メーカーの協力で「いのち輝く」とは、大阪万博の悲しいアイロニー
5月25日「山本理顕シンポジウム」とロールモデル製造協力「東京大学」の「罪と罰」
伊東 乾

東大で「風俗接待」疑惑発覚、政府派遣のコンプライアンス担当者の責任重大
隠蔽体質は問題を大きくするだけ、今こそ東大は襟を正せ
伊東 乾
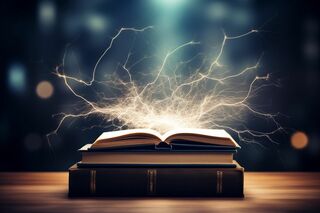
なぜ教育にAIを積極活用すべきなのか、若山牧水・北原白秋の師、尾上柴舟に見るグローバルな芸術の視線
伊東 乾













