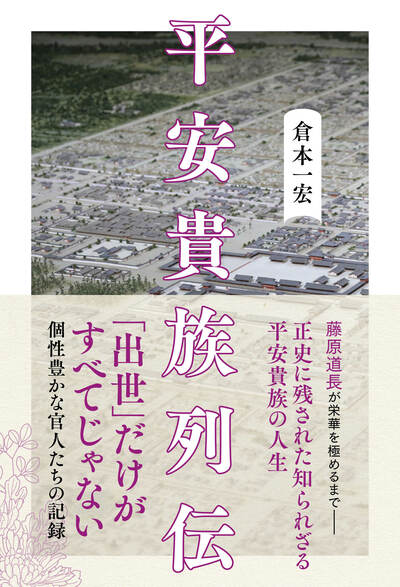武蔵国府(国衙中枢建物跡) 写真/倉本 一宏
武蔵国府(国衙中枢建物跡) 写真/倉本 一宏
(歴史学者・倉本 一宏)
日本の正史である六国史に載せられた個人の伝記「薨卒伝(こうそつでん)」。この連載では藤原氏などの有名貴族からあまり知られていない人物まで、興味深い人物に関する薨卒伝を取り上げ、平安京に生きた面白い人々の実像を紹介します。今回は『日本三代実録』より、紀安雄です。
*この連載(『日本後紀』『続日本後紀』所載分)をまとめた書籍『平安貴族列伝』が発売中です。
地方豪族である苅田氏の出身
紀(き)氏の官人も久しぶりである。『日本三代実録』巻四十九の仁和二年(八八六)五月二十八日丙午条は、紀安雄(やすお)の卒伝を載せている。
前周防守従五位上紀朝臣安雄が卒去した。安雄は、左京の人で助教従五位下種継(たねつぐ)の子である。仁明(にんみょう)天皇は深く経術を崇び、しばしば儒士を招いて、御前で論難させた。時に御船(みふね)宿禰氏主(うじぬし)は大学博士で、種継は助教であった。天皇は二人を召し、経義を議論させた。氏主は礼を執り、種継は伝を挙げて、難撃が往復し、遂に決着が付かなかった。この時に当たって、強力の士である左近衛阿刀根継(あとのねつぐ)と右近衛伴氏永(とものうじなが)は、並びに相撲の最上位である最手であり、天下に無双であった。帝は氏主を名付けて氏永とし、種継を根継として、戯れた。安雄の父は本姓が苅田(かりた)首(おびと)で、讃岐国の人であった。安雄に至って、姓紀朝臣を賜り、京都の人となった。安雄は幼くして学行で称讃された。性格は寛くゆったりとしていて、物事に従順であった。はじめは得業生に補され、天安二年、大学直講となった。貞観(じょうがん)の初年、渤海国王(大虔晃[だいけんこう])が、使を遣わして朝聘してきたが、安雄は存問領客使となった。貞観五年、従五位下を授けられ、助教に転任した。時に勅が下って、有識の公卿や大夫を選んで、格式を撰んだが、安雄はこれに預かった。貞観十一年、遷任されて勘解由次官兼下野介となった。貞観十六年、従五位上に加叙された。貞観十八年、遷任されて主計頭となった。翌年、地方に出て武蔵守となった。政事は簡恵を貴び、官吏も民も、これに安んじた。任期が満ちて京に帰り、元慶(がんぎょう)六年、鋳銭長官兼周防守に任じられた。名声や業績は、武蔵の時よりも減った。安雄はもっぱら経学に詳しく、すこぶる詩歌や文章を美しく作ることに習熟しており、重陽の節では、召されて文人と接した。卒去した時、行年は六十五歳。
紀氏とはいっても、安雄はもともと讃岐国苅田郡の地方豪族である苅田氏の出身である。
父の苅田種継が上京して儒学者として名を馳せ、従五位下助教に至った。安雄はその子である。苅田郡というのは、後に豊田郡と名を替えた、讃岐国でもっとも西にある郡で、現在の香川県観音寺市を中心とした地域である。
こんな地方から中央で活躍する学者が出るとは驚きであるが、当時はまだ、そういったことが起こっていたのである。なお、これも学者出身の菅原道真(すがわらのみちざね)が讃岐守に任じられたのは、安雄が死去した仁和二年の正月のことであった。道真はそれまでは式部少輔兼文章博士であったから、安雄が道真と顔を合わせた機会もあったであろう。讃岐に赴任する失意の道真に、安雄が故郷のことを話していたかもしれない(安雄が種継から讃岐について聞いていれば、また周防守の任を終えて帰京していればだが)。
安雄の卒伝に父である苅田種継のことを詳しく載せているのは、種継の卒伝がないので、合わせて安雄の卒伝に加えたのであろう。
さて、安雄は弘仁十三年(八二二)の生まれ。出生地は平安京の左京であろう。文章得業生を経て、天安二年(八五八)に三十七歳で大学の直講に任じられた。学者としては、別に遅くはない年齢である。
翌天安三年(八五九.貞観元)二月、第二六次渤海使が能登国珠洲郡に来着したのに合わせて、安雄は存問兼領渤海客使に任命された。この渤海使は前年八月の文徳天皇の崩御による諒闇のため、七月に加賀国から放還されている。なお、この渤海使は唐の「長慶宣明暦経(宣明暦)」を伝えていて、この暦が貞観四年(八六二)から貞享(じょうきょう)元年(一六八四)まで、八〇〇年以上も使われることになる。
その功績もあってか、安雄は貞観四年五月に本貫を讃岐国苅田郡から左京に変更されている。名実ともに都人となったのである。翌貞観五年(八六三)に外従五位下、貞観九年(八六七)に四十六歳で従五位下を授けられ、位階も貴族にふさわしいものとなった。十一月には武内宿禰(たけしうちのすくね)の後裔であることを称して、地方豪族であることがわかる苅田首から立派な姓である紀朝臣に改姓され、助教に任じられた。四十六歳の助教というと、ずいぶんと遅い感もあるが、現在の大学の助教と違って、大学は日本に一つしかないのであり、その出自から考えると立派な出世なのであった。
貞観十一年(八六九)には勘解由次官に任じられ、下野介を兼任した。貞観十八年(八七六)には主計頭、貞観十九年(八七七)には武蔵守、元慶六年(八八二)には鋳銭長官兼周防守に任じられ、周防に下向した。この時、六十一歳に達していた。
この間、有識の公卿諸大夫に勅が下って『貞観格式』の編纂を開始したが、安雄もこれに参画している。なお、『貞観格』は貞観十一年、『貞観式』は貞観十三年(八七一)に完成している。
また、武蔵守としては、物事を簡素にして恩恵を施すことを重視し、官人も民衆も非常に満足したというが、周防守としては、武蔵守の時ほどの業績や評判はあげられなかったという。年齢のこともあったのであろう。
仁和二年に六十五歳で卒去しているが、出自の枠を越えた、まことに天晴れな人生であったと言えるであろう。
*『平安貴族列伝』は今回で最終回になります。今までお読みいただきありがとうございました。第39回から最終回、書き下ろしを含む書籍も発刊予定です。
*また、倉本一宏先生の新連載も準備中です。こちらもご期待ください。