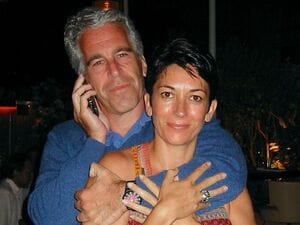ウクライナへの軍事支援の一時停止を指示したトランプ大統領=3日、ワシントン(写真:ゲッティ=共同)
ウクライナへの軍事支援の一時停止を指示したトランプ大統領=3日、ワシントン(写真:ゲッティ=共同)
世界におけるアメリカの役割を大転換させると公言するトランプ米大統領。「世界の警察官」という役割を捨てようとし、「米国第一主義」を掲げ、日米安全保障条約のあり方にも不満を示している。もう一つの大国である中国は、世界を股にかけた経済圏構想「一帯一路」を推進し、覇権的な動きを強める。国際情勢が流動化する中、日本が目指すべき外交戦略とは──。 “石破外交”のキーマンであり、外交・安全保障政策を担当する長島昭久首相補佐官(64)に話を聞いた。(取材は3月4日/前後編の後編)
(河野 嘉誠:ジャーナリスト)
【前編から読む】
石破官邸のキーマンが明かす「トランプ・ゼレンスキー決裂、欧米分断の危機に日本外交はどうふるまうか」
国際秩序を守る意識捨てたアメリカ
──長島補佐官は、野田政権(2011~2012年)でも総理大臣補佐官として、外交・安全保障を担務されていました。当時と現在の違いは?
長島昭久首相補佐官(以下、長島):世界情勢の悪化はあの頃よりもはるかに厳しく、深刻です。だんだんと悪化している点では連続性がある。それと同時に、ある時点から、戦後秩序の破壊がはじまったという意味で、非連続性も感じています。
ターニングポイントは、2014年です。ロシアがクリミアを一方的に併合し、中国が南沙諸島で人工島を造成し要塞化するということが起きた。あのタイミングで、いわば「米中新冷戦」が始まったとみています。
──そこにまた、トランプ大統領が登場した。
長島:非連続性がよりまた一段違うフェーズに入っています。トランプ大統領が、就任演説で最も強調していたキーワードは「常識の革命」です。たとえば、連邦政府の「多様性、公平性、包摂性(DEI)」事業に対する否定をはじめ、国内的にも、これまでの価値観を変容させようとしています。
「常識の革命」は、対外政策においても顕在化しています。アメリカのこれまでの「常識」とは、国際秩序を守るために多少は持ち出しをしてでも踏ん張るという姿勢でしたが、もはやそうではありません。バイデン政権の時は、現実にどこまで履行できたかという問題は別にして、国際秩序のために一肌脱ぐという意識は政府内で共有されてました。
──ウクライナ停戦を巡る動きもしかり、そこが変わってきている。
長島:今回の第2次トランプ政権では、ルールに基づく国際秩序というものに、アメリカがどれだけコミットしていくかということについて、やはりこれまでとは少し異質でしょう。
同盟国のあり方についても同様です。「同盟国は特別」というような既存の価値観に対する反発すら感じます。ヨーロッパへの態度は、まさしくそれですよね。それが今後、日本や韓国に向けられる可能性が全くないのかと考えると、私はそれほど甘くはないと感じています。
──日米安全保障条約や、関税引き上げを巡る問題しかり・・・・・・。
長島:我々としては、引き続きこれは“Win-Win”なんだということをしっかりとお伝えしていく必要があります。アメリカ、日本、そして世界の安定にとって、日米同盟の強化がメリットになるということです。安全保障のみならず、経済的な面でも、「メイク・アメリカ・グレート・アゲイン」に資するものであると伝える続ける必要があります。