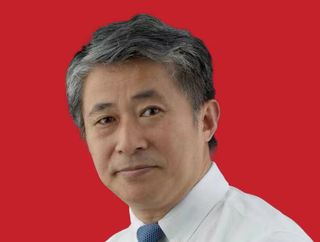中国・鄭州の食品加工工場の様子。2008年撮影(写真:Newscom/アフロ)
中国・鄭州の食品加工工場の様子。2008年撮影(写真:Newscom/アフロ)
(作家・ジャーナリスト:青沼 陽一郎)
いまから20年近く昔のことだ。中国に進出した日本の食品企業の工場をいくつも見て回った。バブル経済が崩壊してデフレに陥っていた当時の日本にとっては、中国が日本の強い味方だった。
そもそも日本にバブルが到来したのも、1985年の「プラザ合意」で円高基調を受け入れたことが引き金だった。その“強い円”を利用して海外に進出する企業も増えた。それで日本の食品メーカーが90年代の後半から、盛んに向かった先が中国だった。
低コストを目当てに中国に続々進出した日本企業
改革開放政策を続ける中国は、人件費も安く、人手も豊富で、距離的にも近い。そこで日本で培った高い加工技術を中国に持ち出し、現地の工場で国内産と同等のものを生産させ、商品を日本へ輸出する「開発輸入」を展開していく。
どこの工場にも従業員の寮が備え付けてあり、地方から集団でやってくる若い労働力を確保していた。だいたい20歳そこそこの女性が多かった。嫁入り前の出稼ぎという意識もあって、名前が書けて、数が数えられさえすれば、即合格で採用された。
そこでやらせていたことといえば、単純手作業ばかりだった。
たとえば、私が最初に目にしたのは、山東省青島にあった工場での「甘エビ」の加工だ。