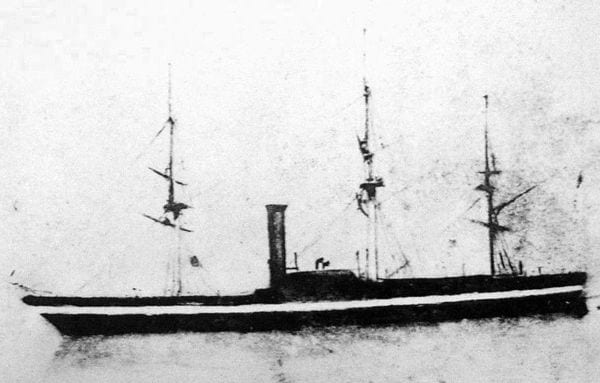 万延元年遣米使節団が乗船したポーハタン号
万延元年遣米使節団が乗船したポーハタン号
(柳原三佳・ノンフィクション作家)
「厚生労働省に入省して、生きながら人生の墓場に入ったとずっと思っている・・・」
8月26日、厚労省の改革若手チームが根本匠厚労相に手渡したというアンケート結果の中の一文です。
その切実な会見内容をニュースで見ながら、少なからずショックを受けました。
『厚労省職員4割超、ハラスメント被害 「加害者が昇進」』(「朝日新聞」2019年8月26日)
https://www.asahi.com/articles/ASM8V54P6M8VUTFK010.html
記事を要約すると、
「パワハラやセクハラ等を受けたことがある」と答えた人は46%、うち54%が「人事上の不利益等を考慮して相談せず」「部局の相談員に相談しづらい」とのこと。
また、人事異動などが「適切になされていると思わない」は37%で、うち38%が「セクハラやパワハラを行っている幹部・職員が昇進を続けている」を理由に挙げた、というのです。
しかし、冷静に考えれば、こうした傾向はいつの時代も、また、どんな会社や団体にも、多かれ少なかれあったのかもしれません。
江戸時代の厳しい身分制度の下で
「開成をつくった男」佐野鼎が生きた幕末から明治初期は、まだまだ身分制度が厳しい時代でした。
1829年、駿河国(現在の富士市)の郷士(ごうし)の家に生まれた鼎は、16歳で江戸へ出て、下曽根信敦という幕臣が主宰する有名な塾に入り、高い学問を身に着け、20歳の頃にはすでに蘭学や西洋砲術のスペシャリストとして一目置かれる存在になっていました。
しかし、彼は身分的には決して高いところにいたわけではありません。
郷士とは農村に居住する武士のことで、武士階級の中では低い地位にありました。ですから、長崎海軍伝習所で第1回海軍伝習(1855年)がおこなわれたときは、正規の生徒に名を連ねられないため、下曽根の息子の「草履取り」という肩書きで現地へ赴き、学んだのです。
師匠の下曽根は、身分は低いけれど能力の高い鼎を、「員外聴講生」として、なんとしてもこの伝習に送り込みたかったのだと考えられます。



















