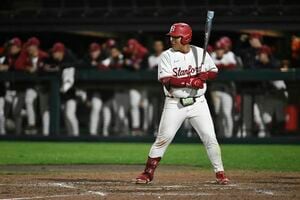毎朝授業の前に実施されるドッジボールでも、活躍したくなかった。目立てばきっと「ハーフ」とか、「外人」といわれる。そうやって珍しがられることは、僕にとっては、悪口をいわれることと同じだった。
「どうして、人と違うことがダメなんだ。悲観する必要も否定することもないじゃないか」
父は何度も何度もそういって、何事にも消極的な僕の背中を押そうとしてくれた。でも、当時の僕にとっては、その言葉は厳しさの象徴でしかなかったし、叱咤されているとしか感じなかった。「父さんはみんなと同じなんだから、僕の気持ちなんてわかるわけない」と思うこともあった。
僕は学校では孤独だった。だけど、幼かった僕はその孤独すら、よくわからなかった。
孤独が嫌だから友だちを作ろうというふうには思わなかった。逆に早くひとりになりたかった。学校でのこの嫌な時間が過ぎていくのを待つだけだ。幼稚園同様に小学校低学年時代に良い思い出はほとんどない。
もちろん、その当時の環境やクラスメートたちを責める気にはならない。ただ、僕自身が非力だったからだ。父がいうように「違うことのなにが悪いんだ」と思えていたら、きっと僕は多くの出会いやチャンスを手にできていただろう。僕が恵まれない幼少期を過ごしたのは、心を閉ざし、壁を築いた僕に責任がある。しかし、当時はそんなふうに思う余裕なんて、一切なかった。兄弟たちも同じ想いをしているんじゃないかと考えることもできなかったのだから。