映像美際立つ『ラストエンペラー』が描く人間の深層
追悼:ベルナルド・ベルトルッチ監督(1)
2018.12.25(火)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください
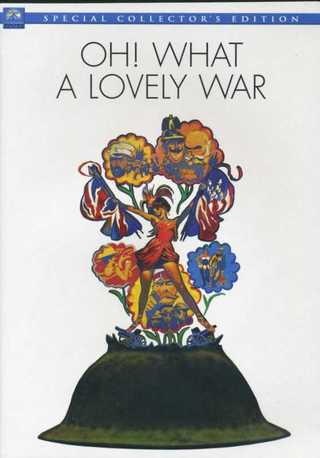
映画が悲しく伝えるナショナリズムの広がる時代
テクノロジーのもたらす限りない進歩の夢と戦争のための戦争
竹野 敏貴

現代史としての映画史、1968年の新しい波
50年前、フランスは、世界は、映画界は、歴史の大波に揺れた
竹野 敏貴

野球の歴史を変えたベーブ・ルースと大谷翔平
映画と旅する歴史の舞台~米国篇(17) 狂騒の時代のヒーローとヴィラン
竹野 敏貴

ポピュリズム政党が躍進した「移民大国」イタリア
映画と旅する歴史の舞台(イタリア篇)~移民「受け入れ国」と「送り出し国」の歴史
竹野 敏貴

ポストトゥルース時代に犬とともに見る世相(その2)
「It’s about the respect」虐げられしものの叫び声が聞こえる
竹野 敏貴
本日の新着

韓国の一大社会問題へ発展した「注射おばさん」と「点滴おばさん」事件
医師免許を持たず規制薬物を芸能人に日常的投与か
アン・ヨンヒ

でっち上げた疑惑でパウエル議長を刑事捜査、トランプの狙いは「FRBの隷属」、中央銀行の独立性をいとも簡単に蹂躙
木村 正人

地政学・経済安全保障から見て2026年には何が起きるのか?専門家が選定した10のクリティカル・トレンドを読み解く
【オウルズレポート】ベネズエラ軍事作戦と対日輸出規制で幕を開けた2026年、企業はどう備えればいいのか
菅原 淳一

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
誰かに話したくなる世界遺産のヒミツ(20)「アユタヤ歴史地区」(タイ)
髙城 千昭









