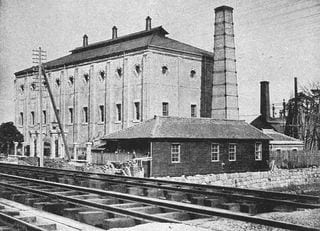明治、大正の時代に活躍した実業家、渋沢栄一。彼は約500の企業に関わるとともに、約600の社会事業にも力を注いだ。一般的に「近代日本における資本主義の父」と呼ばれるが、さらに広く「近代日本を創った存在」と言っても過言ではないだろう。
前回の記事:「『良妻賢母』を育て国力を押し上げた渋沢栄一」
「医療・福祉や教育、外交など、渋沢は幅広く社会事業に携わりました。とはいえ、彼は決して慈善事業に熱かっただけの人ではありません。むしろ日本経済の成長を考え、きわめて合理的に社会事業を行ったといえます」
こう語るのは、國學院大學経済学部の石井里枝(いしい・りえ)准教授。渋沢の社会事業にこそ、彼の信念である「道徳経済合一」の概念が色濃く出ているという。特に顕著なのは、国際人としての渋沢が行った民間外交だ。
本連載の最後となる今回は、渋沢の外交活動を紹介しながら、彼が追い求め続けた道徳経済合一の本質に迫る。
 國學院大學経済学部准教授の石井里枝氏。東京大学経済学部卒業。同大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。三菱経済研究所研究員、愛知大学経営学部准教授を経て現職。著書に『戦前期日本の地方企業‐地域における産業化と近代経営‐』(日本経済評論社)、『日本経済史』(ミネルヴァ書房)などがある。
國學院大學経済学部准教授の石井里枝氏。東京大学経済学部卒業。同大学院経済学研究科博士課程修了。博士(経済学)。三菱経済研究所研究員、愛知大学経営学部准教授を経て現職。著書に『戦前期日本の地方企業‐地域における産業化と近代経営‐』(日本経済評論社)、『日本経済史』(ミネルヴァ書房)などがある。
アメリカの排日移民に抵抗。その裏にあった「合理性」
――前回、渋沢が関わった医療・福祉、教育の社会事業を聞きました。今回は、諸外国に対しての外交について聞きたいと思います。
石井里枝氏(以下、敬称略) 渋沢は国際人であり、民間外交を行った人としても数多くの功績を残しています。もともと彼は20代で一橋家に仕えましたが、27歳となった1867(慶応3)年に、バリ万博使節団の一員としてヨーロッパを歴訪します。
そこで見た欧州の文化や産業は、その後の彼の事業にさまざまな影響を与えました。そしてこの頃から、海外の情報を積極的に取り入れ、国際的な視野で物事を考えていたと言えます。
そうして、渋沢は民間人でありながら諸外国との外交活動を行いました。代表例が、1909(明治42)年に結成された渡米実業団です。