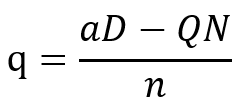スイス・ジュネーブで、人工知能(AI)に関する会議に登場した人型ロボットの「ソフィア」(2017年6月7日撮影)。(c)AFP/Fabrice COFFRINI〔AFPBB News〕
今回も前回に引き続きR&D最先端のお話です。
国際的にAI開発が注力され、IoTやユビキタス情報化が推進されるなか、これらの環境全体で同時に発生、進行する「知のリスク」と、それに対する東京大学の取り組みの1つをご紹介しましょう。
ここ数年「AIでなくなるこの職業」といった特集はしばしば組まれ、私自身もそのようなコラムを幾度も書いてきました。ただしほかとは少し違う切り口になっていると思います。
すなわちAIが本質的に得意なこと、また全く得意でないことを原理的に区分けして、得意でない部分、人間にこそ可能な部分を伸ばそう、という議論を展開するように心がけてきました。
そこで触れていないもう1つの観点、2000年から一貫して大学で取り組んでいる「知識構造化」の新しい取り組みについて、今回は原著相当を初めて公刊する場としてJBPを選んで記してみたいと思います(そのため末尾に梗概を付しています)。
それは「知の死角」という問題系です。
自動化で見えなくなるもの
機械学習が進み自動化が進展すれば、人間の手を煩わされずに済みます。
都市部の駅改札では検札の係員をほぼ見かけなくなりました。自動改札の普及、これにより、一人ひとりの旅客が改札を通るときの定期や切符、プリペイドカードについて、人間の係員が目を通すことはなくなった。
でも、もし問題があれば後からログをチェックすることなどはできるはずです。
もっと簡単な例を挙げれば、洗濯機の普及で主婦は服を洗うのにかける手間隙が激減しました。私が子供だった高度成長期に白物家電として冷蔵庫、洗濯機、炊飯器、電子レンジ、エアコンなどが普及し、ほぼ飽和するに至る過程を目撃しました。
しかし、いまだ戦後色の残る昭和40年代初め、井戸端で金だらいに洗濯板でごしごしやってる奥さんを目にしたものです。