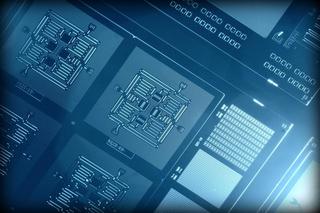昭和の未解決事件にまつわる3冊の本を紹介します(写真はイメージ)
昭和の未解決事件にまつわる3冊の本を紹介します(写真はイメージ)
未解決事件には時に、強烈な魅力が宿ることがある。事件という、何らかの被害者が存在する事柄に対して「魅力」という表現を使うことは適切ではないかもしれないが、そうとしか呼べない何かを持つ事件がある。
例えば「グリコ・森永事件」「三億円事件」「下山事件」。どれも昭和史を賑わし、現在に至るまで様々な憶測が語られ、物語などでも頻繁に使われる未解決事件だ。
それら未解決事件に、一般的なノンフィクションとは異なるアプローチで挑む作品を紹介しようと思う。うち2冊は小説である。そしてもう1冊は、親族の証言を元に事件取材に挑むというなかなかない切り口のノンフィクションである。いまだ解決されていない事件だからこそ持ちうる余白をどう埋めるのか。それぞれのアプローチを紹介しよう。
グリコ・森永事件を題材に描かれた「家族」
塩田武士『罪の声』
お菓子に毒を持ったと企業を脅迫し、社会を混乱に陥れた「グリコ・森永事件」をベースにした小説である。「グリコ・森永事件」について徹底的に取材を積み重ねた末に生まれた、作家的想像で埋めた部分以外のリアリティを圧倒的に追求した小説である。
京都市に「テーラー曽根」という店を構えている曽根俊也は、ある日、母からの頼まれものを探している途中で、見覚えのないものを見つける。自分の子どもの頃の声が収録されたカセットテープと、製菓メーカーの「ギンガ」「萬堂」の文字が書かれた黒革のノートだ。
まさか。
ネットの検索で俊也は、このテープは、戦後最大の未解決事件と言われる、複数の製菓・食品メーカーを恐喝した大事件「ギン萬事件」で、電話越しの脅迫で使われたものだ、と知ることになる。
スーツの仕立て一筋だったはずの父と「ギン萬事件」はどうしても結びつかない。だとすれば誰か親族が関わっているとでも言うのか・・・。俊也は、父の幼馴染である堀田に相談をし、可能な範囲で「ギン萬事件」と曽根家との関わりを調べることにする。
一方で、大日新聞文化部の記者である阿久津英士は、社会部の鳥居からメチャクチャな指令を下される。大日新聞は年末に昭和・平成の未解決事件の特集を組むことが決まっており、ギン萬事件絡みでロンドンに取材に行けと言うのだ。その後専従としてギン萬事件に関わることになる阿久津は、様々な資料を読み込み、鳥居の嫌味をなんとかかわしながら、できる範囲で取材を続けていく。あらゆる方向から取材を続けた阿久津は、ついに突破口となる大ネタを手にするが・・・。
というような話です。
この物語の凄い点は、ただ戦後の未解決事件をベースにして小説を書きました、というものではないということだ。この物語には、はっきりと「家族」というテーマが見える。現実の事件という事実に、まったくの虚構を丁寧に組み合わせることで、そこに家族の物語を現出させたのだ。日常を舞台にしては描くことが出来ない家族の形や人生を描くために、戦後最大の未解決事件という舞台を選んだ。そういう必然性のある物語なのだ。
物語の発端が、俊也が見つけるテープだというのも、家族が根幹となっている物語である所以だ。僕自身は、脅迫電話に子どもの声が使われていたということさえ知らなかったが、「グリコ・森永事件」を調べ続けた著者は、声を使われたあの子どもは今どうしているのか、という関心からスタートさせてこの物語を紡ぎあげた。
事件には被害者家族と加害者家族が必ずいるが、未解決事件の場合、加害者家族は表沙汰にならない。表沙汰にならないがゆえに、差し伸べられたかもしれない支援の手も届かなくなる。では、今どうしているのか? その余白を、著者は作家的想像によって丹念に埋めようとするのだ。
これはもちろん、ノンフィクションという手法では実現できないことだ。物語によって余白を埋めることは一見簡単そうだが、著者は「ギン萬事件」を「グリコ・森永事件」をベースにして細部まで忠実に描き出す。明らかになっている事実を捻じ曲げることなく、明らかになっていない部分にぴったりとハマる虚構を用意することは並大抵のことではないだろう。物語が持つ可能性を最大限利用しながら、未解決事件の背景にあったかもしれない家族の物語を描き出す。珠玉の一冊だ。
三億円事件の真犯人が告白?
中原みすず『初恋』
現金輸送車を白バイ隊員に扮した犯人が止め、鮮やかに現金を奪い取った「三億円事件」を背景に据えた小説である。しかし、そんな表現では物足りない、衝撃的な作品だ。
なぜなら著者は、本書の中で自らの犯行を告白しているのだ。
中原みすずは、両親を失い親戚の家をたらいまわしにされ、どこにも居場所がないと感じている。ある男に襲われそうになったことで男性不審にもなり、何をするでもなく、なんでもない灰色の毎日を送っていた。
そんな彼女が向ったのは、ジャズ喫茶<B>だった。店先で出逢った女性に誘われるがまま店内へと入っていき、そこで毎日のようにたむろしている、亮を中心としたグループと出逢った。それからみすずは、<B>で過ごす日々が日常になっていく。ようやく居場所を見つけたのだ。
ある日、亮のグループの1人である岸から相談を受けた。力になってくれないか、と。現金輸送車を襲う手助けをしてくれないか、と。<B>に通う内に岸に惹かれるようになっていったみすずは、岸のその言葉に耳を傾ける。そうしてみすずは、あの三億円事件を実行することになる。
そう、この作品は、「三億円事件を実行した」と語る著者自身による小説なのである。
この物語の真偽は僕には判断できない。誰にもできないだろう。著者は小説の中で、<B>で一緒に過ごした面々は皆死んでしまった、というようなことを書いている。この物語がもし真実であるとすれば、著者がこの物語を書くことで迷惑を被る人間がいなくなったから書けた、とも考えられる。それはすなわち、著者の主張を裏付ける方法がほとんど存在しないことを意味する。
僕の印象を書こう。僕は本書を読んで、著者の中原みすず氏が三億円事件の犯人なのだろう、と感じた。そう感じた理由は、ここでは書かないことにしよう。どのみち、僕がどう思おうが、著者が三億円事件の犯人であるかどうかにはまるで影響しない。仮にこの小説で描かれていることが真実であるとしても、それを証明する手段はないのだ。他の真犯人が明らかになった、というようなことでもない限り、この物語を真実の1つとして扱うことに不都合はない。
三億円事件は、三億円という当時としては相当な被害額であることや、大量の遺留品を残すことで捜査を撹乱させたなどの手際の部分に注目が集まることが多い。しかし、もしこの物語が真実であるとすれば、三億円事件の本質は中原みすずの岸という男への好意にあるということになる。それは、三億円事件という未解決事件を見る新たな視点となるだろう。この物語が真実であるかどうかはともかくとして、こういう新たな見方を提示出来るというのもまた、物語が持つ可能性なのだと感じる。
「下山事件は兄がやったかもしれない」
柴田哲孝『下山事件 最後の証言』
初代国鉄総裁である下山定則が線路上で死体で発見された「下山事件」を扱ったノンフィクションである。
普通ノンフィクションというのは、ノンフィクション作家が自分とは関わりのなかった事件や出来事を取材し、作品として発表するものだ。今も語られる未解決事件であればなおさら、著者自身と事件自体に繋がりがあることの方が稀だろう。
本書の場合、事情が異なる。著者・柴田哲孝氏が真っ先に取材をしたのは彼の大叔母であり、その大叔母は、「下山事件は兄がやったかもしれない」と発言したのだ。
大叔母の兄とはつまり、柴田哲孝の祖父である。つまりこの作品は、「下山事件」という重大な未解決事件に親族が関わっているかもしれない、という疑惑を追及するために取材を続けるという、かなり特異なノンフィクションなのである。
もちろん、著者は真実を追う者としての矜持を手放しはしない。尊敬する祖父を糾弾することになるかもしれない取材ではあるが、著者は可能な限り感情を排し、真実を明らかにしようと動き続ける。普通のノンフィクションであれば、読者が取材を続ける者の内面を推し量ることはあまりないが、本書の場合は、著者はどんな気持ちで取材を続けたのだろうか、と考えてしまった。
「下山事件」は、単に1つの事件というわけではなく、昭和を舞台にした様々な策謀の1つの結果なのだということが本書を読むと理解できる。物事が複雑に絡まり合い、追えば追うほど深みにはまっていく。当時の国際情勢との絡みや、日本の中枢を担う者たちまで関与する壮大な背景は、「グリコ・森永事件」や「三億円事件」など、個人や小さなグループによる犯行だろう事件とはまた違った凄みを感じさせる。「下山事件」そのものではなく、昭和の裏面史として読んでも興味深い内容だろうと思う。