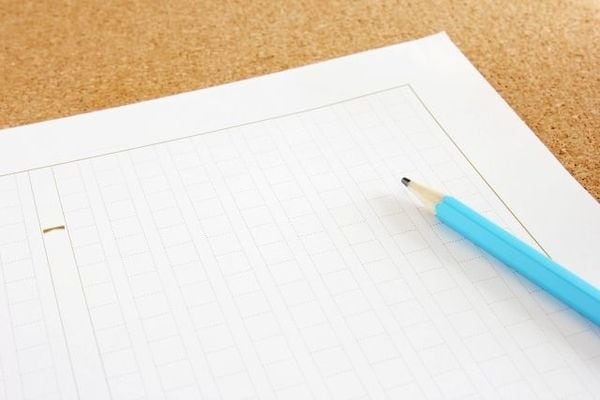 書けないものは書けない(写真はイメージ)
書けないものは書けない(写真はイメージ)
(文:栗下 直也)
この原稿は本来は2016年8月30日の午前7時までに公開しなければならなかったのだが、現在、9月1日の午前9時をまわろうとしている。
このまま沈黙を守るわけにもいかず、無理矢理書き出したのだが、原稿用紙5枚程度の分量に過ぎなくても、すんなり書き終える自信がない。いや、延べ90人の作家の〆切に関する文章を集めた本書『〆切本』を読むと、そんなにすらすらと書いたらいけない気すらしてくる。
王道の手段、「仮病」
〆切は確かに守らなければならないのかもしれない。大学人だった森博嗣は〆切にルーズな出版業界を「かなりの非常識」と指摘する。吉村昭のように「締め切り日前に必ず書き上げ、編集者に渡すのを常にしている」のは例外なのだろう。〆切があることで人間は頑張れると聞くが、〆切があっても頑張れない人間もいるのである。
「内向の世代」の代表的な作家の後藤明生は文学賞のパーティーに行く途中の電車ですでに2日延ばしてもらった〆切りがもう1日延びないかを願う。「まことに、われながら情けない話であるが、それはもうはっきりしていた。出かけたが最後、どうしても一次会だけで切り上げて来るということが、わたしには出来ない」。気持ちがわかりすぎる。
『野火』などで知られる大岡昇平。大岡の息子は記者にお父さんみたいに作家になりたかと尋ねられ「終始うそをついてあやまってばかりいなければならないからいやです」と答えた。大岡はこう記している。「一枚も出来ていないのに、『十枚まで行ったとこなんですが」とか、『不意に客がありましてね』とか、風邪を引いたとか、腹が悪くなったとか、苦しい口実を発明する現場を見られていたわけである」。
確かに、仮病は締め切りを先延ばしする手段としては王道だ。















