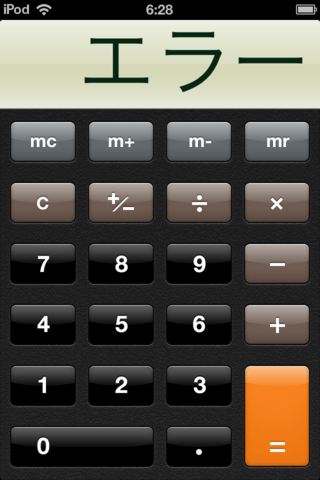物心ついたときから、なんとなく不安感とともに生きてきたように思う。
それもそのはず。黄色人種では、「幸せホルモン」といわれるセロトニンを運ぶセロトニントランスポーターの働きが弱く、ラテン系の人々や黒人はこの働きが強いと言われている。
その差はセロトニントランスポーターの遺伝子タイプの違いにある。セロトニンの量が少ないと、不安やうつになりやすいとされるので、日本人は遺伝子レベルで絶望を感じやすいらしい。
絶望という言葉を目にすると、タモリの顔が思い浮かぶようになってしまった。タモリは自分にも他人にも期待していないとの論理を展開し「タモリ=絶望大王」説を唱えた樋口毅宏の書籍『タモリ論』を読んだのがきっかけだ。
また、堺雅人主演のドラマ「Dr.倫太郎」において、精神科医である主人公の日野倫太郎は、ことあるごとに「僕の尊敬するコメディアンが」と、心を病んだ患者に対してタモリの言葉を、決め台詞として引用していた。
タモリのサングラスの奥にある「真意」をここで暴きたい気持ちはやまやまであるが、前述した『タモリ論』という傑作に勝る論理展開はできそうにない。他にタモリに絡めて3冊紹介するということも難しいので、今回は「絶望」のほうについて3冊を挙げて考察したい。
その前に、唐突だがここで問題。あなたのなかで絶望とは何色でイメージされるだろうか。もしよければ回答を用意したうえで、本コラムを読んでみていただきたいと思う。
『悪人』を超える超大作
『怒り(上)(下)』(吉田修一 著、中央公論新社)
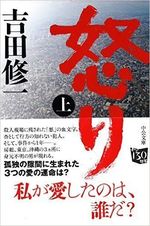 『怒り(上)』(吉田修一 著、中央文庫, 600円、税抜)
『怒り(上)』(吉田修一 著、中央文庫, 600円、税抜)
この本の作者である吉田修一は、同時代に生きていることを感謝したくなる当代随一の作家である。
昨年、又吉直樹が受賞して話題を集めた純文学の登竜門とされる芥川賞を『パークライフ』で受賞した。そして、同じ年に山本周五郎賞という、一般的には直木賞に次ぐ(業界内では周五郎賞のほうが信頼度は高いという人が多い)位置づけの大衆文学賞も受賞している。まさに文学界のハイブリッドだ。
『怒り』は、その吉田修一の魅力が十分に発揮された作品であり、今年の秋に映画が公開予定である。この『怒り』にテイストが似た作品で、数年前に吉田修一原作として映画化された『悪人』は大ヒットを記録したので、期待に胸を膨らませている人も多いのではないだろうか。
きっとその期待は、いい意味で裏切られるだろう。なぜなら、物語の構造において『怒り』のほうが、数倍すごいからである。