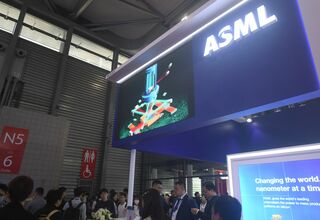STAP論文に対する2本の反論(BCA)と総説を掲載したNature誌(筆者撮影)
STAP論文に対する2本の反論(BCA)と総説を掲載したNature誌(筆者撮影)
9月24日、科学雑誌Natureが3本の記事を載せた。このうち2本は昨年、日本を騒がせたSTAP細胞の論文(以下、STAP論文)に関する“反論”で、残りの1つは総説だ。3本はそれぞれ独立した記事だが、互いに関連している。
いずれもSTAP細胞の騒動に、科学界としての決着をつける記事だ。しかし、まだいくつかの疑問は残る。それは、Nature誌自身の役回りについてだ。
今回Nature誌に載った記事を紹介する前に、STAP論文とそれをめぐる不正告発の経緯を簡単におさらいしよう。すでによく知っているという方は、「すでに撤回された論文への反論」から読んでいただきたい。
画期的だったSTAP細胞
2014年1月末にNature誌に掲載されたSTAP論文は、身体中のすべての細胞だけでなく、胎盤にも分化することのできる細胞に関するものだった。赤ちゃんマウスの細胞を弱酸性の液に30分ほど浸けるなどの簡単な手法で、万能細胞であるSTAP細胞へと変えることができたという。本当であればまさに画期的だ。刺激によって細胞を受精卵に近い状態に若返らせる(初期化させる)ことが可能になると分かったからだ。
STAP細胞自体は培養皿の中で維持するのも増やすのも難しいが、培養条件を変えれば、それも可能になる。そうやってできるのが「STAP幹細胞」と「FI幹細胞」だ。
STAP幹細胞は胎盤には分化できないという点からもES細胞やiPS細胞に非常によく似ていた。これは、ES細胞のように胚を壊したり、iPS細胞のように遺伝子導入をしたりするといった手段をとらずに、幅広い応用が期待できる多能性幹細胞を入手できることを意味する。
FI幹細胞の方は、増殖速度は遅いが、胎盤と胎児の両方に分化できるというSTAP細胞の性質を引き継いでおり、科学的に興味深い細胞だった。
STAP論文は、その革新的な中身だけでなく、若い女性である小保方晴子氏が筆頭著者だったことからも大いに注目を集めた。共著者には、世界的に知られた笹井芳樹氏、若山照彦氏、丹羽仁史氏といった理化学研究所 発生・再生科学総合研究所(当時、理研CDB)のスター研究者、さらにはハーバード大学のチャールズ・ヴァカンティ氏らが名を連ねていた。
不正の判定、それでも「STAP細胞はある」
首相や文部科学大臣までが公の場で言及するほどの歓迎ぶりで迎えられた研究だったが、1週間も経つと論文に載っている写真に改ざんの形跡があるなどの疑義が指摘され始めた。