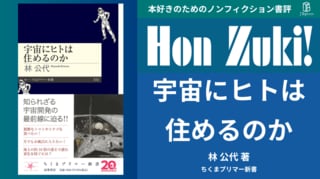2カ月ほど前のこと。「ミュールーズの博物館に、私の仕立てた着物が飾られることになった」と、友人の大矢祐子さんが教えてくれた。
日本の着物がフランスの博物館を飾った
 ミュールーズ染色博物館
ミュールーズ染色博物館
この祐子さんこそ、私がアルザスに行くたびにお世話になる方。ご主人の仕事の関係で、今はアルザスのセレスタという町に暮らしているが、日本で相当なキャリアを積んだ和裁士である。
着物の国、日本であればこそ、仕立ての仕事は貴重であるけれども、「フランスでは残念ながら機会がないのでは」と誰しもが考える。
けれども、そこはフランス。美そのもの、またそれを形にする腕に対しては賞賛を惜しまない。
祐子さんの才能を聞きつけて、ぜひ自分のために着物を仕立ててほしいというマダムが、ここにはちゃんといるのである。
着物といっても、祐子さんがこちらで製作しているのは、日本の伝統的な着物地を使ったものばかりではなく、ヨーロッパのオートクチュールの布が材料だったり、形も羽織のフォルムをベースにしたガウン風のコートありと、ヨーロッパの女性により似合いそうな感覚で創作されたもの。
日本人の既成概念からは一歩足を踏み出したと言えるものだ。
目に見えないところへのこだわりが真の美を生む
 館内には、日本の小紋染めの反物も展示されていた
館内には、日本の小紋染めの反物も展示されていた
ミュールーズの博物館に飾られることになったのは、ギャラリーを経営しているマダムからの依頼によるもので、この地方で生産されている布地を使って、それこそ伝統的な日本の着物の形に仕立てるというもの。
「裏地として持って来られたのが、コテを当てると溶けてしまうような化繊だから、そこが大変だったわ」と、祐子さん。
なるほど、上質の絹を扱い慣れているプロ泣かせのイレギュラーな注文には違いない。
その作品を観るために、私はミュール―ズの博物館に出向いた。
祐子さんが仕立てた着物は、現代のこの地方の布を扱うコーナーでスポットを浴びて立っていた。
プリント柄というのは、ちょうどゆかたの模様のように、一枚の布の上に一定の間隔を置いてモチーフが繰り返し表れるものだが、裾模様になる部分にポイントが来るように、しかも、おくみと身ごろの継ぎ目でもそれがずれずにつながるように柄合わせがされていて、着物の格付けからいうと数段上の、いわゆる絵羽模様の着物に匹敵するような具合で仕立ててある。