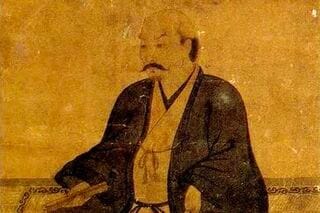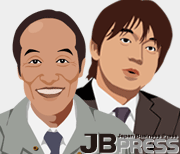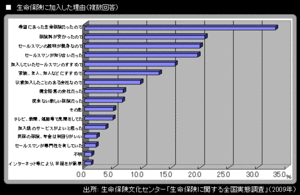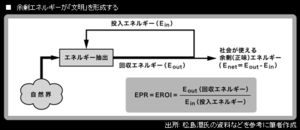株主主権主義が中長期的な研究開発の障害に
これとは逆に、80年代の米国では、大企業の自前主義に翳りが見え始めた。新自由主義的な潮流により、株主主権主義が台頭。経営者は4半期毎に成果を求められ、腰を据えて中長期的な研究開発に取り組むことが評価されづらくなった。
さらに、レーガン政権が設立した産業競争力委員会が1985年にまとめた「ヤングレポート」に沿う形で、知的財産重視の産業構造へと方向転換が図られる。イノベーションの場として大学が重視され、研究・開発と事業化を大学とベンチャーに任せる「シリコンバレーモデル」が普及し始めた。
アイデア、経営のプロや技術者、資金がコラボレーション(協働)するシリコンバレーモデルは、まさにオープンイノベーションであり、地域社会自体がインキュベーターの役割を果たした。
そして1990年代になると冷戦が終結し、グローバル化とIT革命が進行し、一気に知識社会への移行が鮮明になった。そうなると米国の大企業は自らの強みに集中する「コアコンピタンス」なくして生き残れない状況となり、体質改善が進んだ。
同時に、このような状況に適合したシリコンバレーモデルが飛躍的に拡大し、ベンチャー企業がIT産業を中心とした新産業の牽引役となり、また大企業も戦略的にベンチャー企業とパートナーシップを結ぶことで再生し、米国経済を再活性化したのである。
一方、日本はと言えば、1985年のプラザ合意による円高不況を辛うじて切り抜けたものの、「ナンバーワン」気分から抜け切れず、1990年代のグローバル化とIT革命に乗り遅れてしまった。その上、新自由主義の影響で、1980年代の米国と同様、短期的な成果を求められるようになる。すると、日本の優位性であった内部留保による中長期的投資が困難になり、長期不況に沈んでいったのだ。
この時代、日本でもシリコンバレーモデルの影響を受けて、産学連携が謳われ、また、多くの大企業で社内ベンチャーが誕生した。しかし、それらが大企業の体質を変え、経済を再活性化するまでには至らなかった。