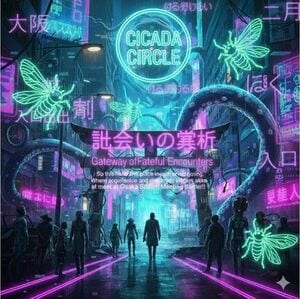先に触れた安倍晋三首相の「再チャレンジ」もそうだし、福田康夫首相も「改革の方向性は変えずに、生じた問題には処方箋を講じていく」として、格差問題に取り組む考えを強調していた。麻生太郎首相に至っては、「行き過ぎた市場原理主義とは決別する」と言い切っていた。
これでも不足だというなら、どんな形で説明しろというのか。野党の言うように、衆院解散・総選挙で国民の審判を仰げ、ということだろうか。そんなに頻繁に衆院解散していたら、日本の政治は疲弊し、ますます劣化するだけだろう。
検証作業でもう1つ気になるのは、別の立場から批判しているのに、いずれも「自公政権に辛口」という評価になってしまうことだ。再び読売新聞から引用する。
「格差・二極化が問題視される中、財政再建優先の政策に固執し、格差是正に向けた実質的な取り組みはなされなかった」(連合)
「安倍内閣以降、徐々に反構造改革のプロセスが進み、麻生内閣で決定的になった。内閣が替わる度に改革姿勢が後退し、おかしな方向にぶれていった」(チーム・ポリシーウォッチ)
連合は民主党の支持組織だし、チーム・ポリシーウォッチは竹中平蔵・元経済財政相が作ったシンクタンクだ。それぞれのバックグランドを知れば当然の指摘なのだが、それが朝日新聞1面トップの見出しのように、「自公の4年 辛口採点」と報じられてしまえば、政権に与えるマイナスイメージだけが肥大化する効果を生むだろう。
おかしさの元凶はどこに
マニフェスト選挙導入以前と比べて、何がどう変わったか。選挙報道が以前より政策を重視するようになったというプラスの変化はある。だが、どう贔屓目に見ても、各党のマニフェストはそれほど立派な中身ではない。むしろ、サービス合戦の部分は、「守られないもののたとえ」と揶揄された過去の公約よりもレベルが下である。
公約通りに実行したかどうかを問うマニフェスト検証にも、かつての一般消費税のような不健全さが垣間見える。
このように見てくると、マニフェスト選挙の導入前も後も、そんなに本質は変わらないのではないか、という当然の疑問が首をもたげてこよう。
だが、眼前で演じられているマニフェスト選挙は、あくまで導入前はひどくて、導入後は前よりはましになっているという前提で話が進んでいる。なぜなのだろう。
筆者なりの仮説がある。
マニフェスト選挙の提唱者が、政治学者を中心とする「有識者」だからなのではないだろうか。
学者の特徴は、自身の学説にこだわるなど、過去の発言や言動との整合性を非常に重んじることだ。しかも、「有識者」だから、間違いなどあってはならないし、あるはずもない。理屈にとらわれやすい環境が整っているのである。
21世紀臨調の名簿を見ると、錚々たる顔ぶれである。政治学者では、共同代表の佐々木毅(元東京大学総長)、西尾勝(東京市政調査会理事長)、幹事会メンバーの主査に曽根泰教(慶応義塾大学教授)、飯尾潤(政策研究大学院大学教授)の各氏が名を連ねている。運営委員まで広げると、マスメディア各社の政治部長や部長経験者がずらりと並んでいる。
学者もマスメディアも、マニフェスト選挙を連名で提言した以上、「なかなか現実とはうまくいかない部分がある」というような発言はしにくいのではないか。しかも、佐々木氏らは、政治学者の世界では大御所的な立場である。若い政治学者が異を唱えることは、師匠に弓引くような行為になるので、なかなかしにくいだろうと推察する。
そうした特殊な環境が、各党のマニフェストは検証されるのに、マニフェスト選挙に対する検証――現実の政治に照らしてうまくいっているかどうかを点検する作業が起こりにくい遠因となっているように思えてならない。