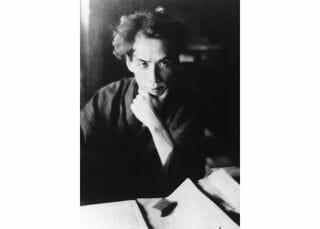カラフルなE131系が走る鶴見線。車両は新型だが、独特で特徴がありすぎる都会のローカル線を思い思い楽しもう
カラフルなE131系が走る鶴見線。車両は新型だが、独特で特徴がありすぎる都会のローカル線を思い思い楽しもう
(山﨑 友也:鉄道写真家)
ルーツはセメントの原材料の輸送
川崎市や横浜市といえば神奈川県を代表する大都市であるが、その都会のイメージからは全く想像がつかないローカル線が両市に存在している。しかもそれがJR東日本に属しているというから驚きだ。知る人ぞ知るその路線とは、なんと日本屈指の工業地帯を走る鶴見線である。
鶴見線は東海道本線の鶴見駅から扇町駅を結ぶ本線と、途中の浅野駅や安善駅から延びる2つの支線で構成されている。車両は近年E131系に代わったため新鮮味はあるが、編成は3両と短めで、距離も3線あわせてたった9.7kmと、都市部のJRの路線にもかかわらずローカル色は否めない。
なぜ鶴見線がこのような運行状況なのかは、その生い立ちに起因している。鶴見線のルーツは1926年に開業した鶴見臨港鉄道で、敷設したのは日本のセメント王ともいわれ、十五大財閥のひとつともなった浅野財閥の創業者浅野総一郎だ。鶴見沿岸を埋め立てて自身が礎を築いた京浜工業地帯への貨物輸送を目的として設立したのである。当時浅野はセメントの主原料である石灰石が埋蔵する西多摩の鉱山をどんどんと手に入れていた。
そして青梅鉄道(現在の青梅線)や五日市鉄道(現在の五日市線)、南武鉄道(現在の南武線)に出資して傘下に収めた結果、沿線で産出された石灰石はこれらの鉄道を経由してセメント工場がある鶴見臨港鉄道まで一気に輸送することが可能となったのだ。ところが戦時の鉄道体制を強化する名目から鶴見臨港鉄道は1943年に国に買収され、以後は国鉄を経て現在に至っている。
このような性格のため路線は臨港部の工場に向かって延びることとなり、南武支線を加えた路線図はまるで右手を下に降ろしたような形にもみえる。
余談だが京浜運河の開削のためにさらった土砂を投棄していた現在の扇島あたりは、次第に砂州となりその後海水浴場として発展した。1930年には旅客営業も開始した鶴見臨港鉄道は海水浴前駅を夏季限定で開業させ、多くの海水浴客を運んだという。