違法風俗店経営の「国立大学准教授」とSTEAM教育の終焉
生成AI以降、法と倫理の分別つかない技術者は有害無益
2025.6.13(金)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
あわせてお読みください

P活女子と薬物パーティ、埼玉の全裸タクシー爆走、国立大教員の違法メンエス副業…最近の日本はちょっとおかしい?
【5月のちょっと気持ち悪いニュース】漂流し始めた日本社会
三田 宏
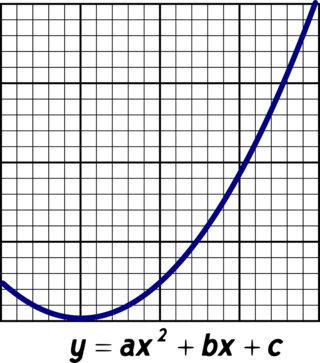
AIが普及したいま、「微分」の初歩は中学校で教えなさい!
子供の興味を引き出す「スケボー」などの応用問題
伊東 乾
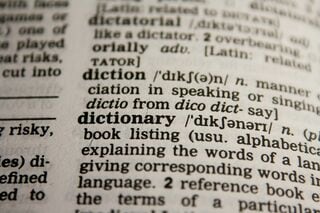
AIを活用して俳句を作る、これが「邪道」ではなく「正統」な理由
正岡子規も切望した19世紀最新技術「辞書」の電子化、金子兜太も苦吟した推敲の本質
伊東 乾

大阪万博で大量発生中のユスリカ対策、実は殺虫剤より効果的な小魚
1950年代に八丈小島で奇病「バク」を根絶したそのパワー
伊東 乾

トランプ政権のハーバード攻撃は日本復活の絶好のチャンス、優秀な留学生受け入れ競争に負けるな
「コスモポリタン」だけがチャンスを生かすことができる
伊東 乾
世界の中の日本 バックナンバー

なぜ古代日本では遷都が繰り返されたのに、平安京で終わったのか?古代日本の宮殿と遷都が映し出す権力と政治
関 瑶子

「ヒロシマのタブー」避け、硬直化し定型化した語りで「核兵器なき世界」を実現できるのか
宮崎 園子

2026年、重要性増す社会的情動スキルとステージマネジャー猪狩光弘の凄技
伊東 乾

AIのお試し期間は2025年で終了、2026年に顕在化する5つのトレンドとAIで稼ぐ企業・コストになる企業を分ける差
小林 啓倫

子供の能力を伸ばす「非認知能力」教育の誤解と正解
伊東 乾

反ムスリム土葬墓論はなぜ間違っているのか?そもそも神道は土葬が前提、土葬が公衆衛生上良くないという論法も乱暴
鵜飼 秀徳



