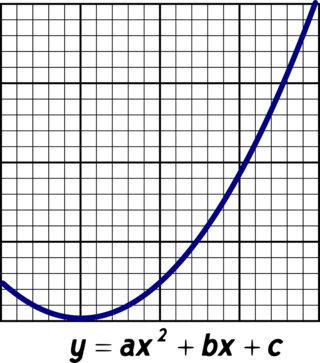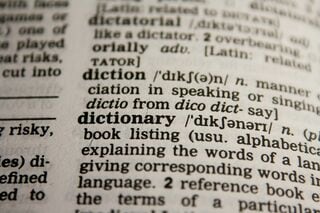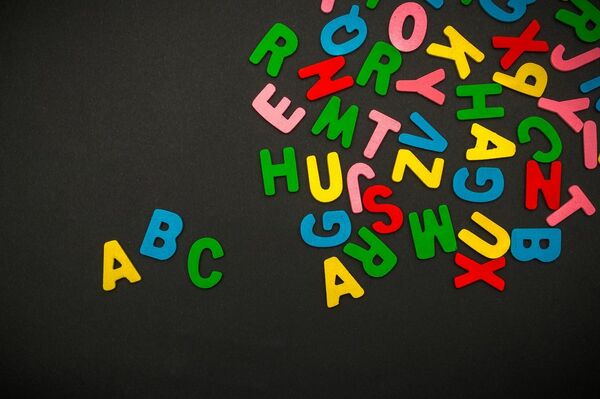 Mahesh PatelによるPixabayからの画像
Mahesh PatelによるPixabayからの画像
読者の皆さんは「外国語活動」という「科目」をご存じですか?
身の回りの大人10人ほどに尋ねてみましたが、それに関連している人、あるいは小学生の子供がいる人3人を除いて、7割方は「何それ?」という反応でしたので、まずそこからスタートしたいと思います。
「外国語活動」は小学3、4年生が履修することになっている必修科目で、現実には「英語」のこと。
年間35単位時間「程度」の履修が定められています。1コマ45分なら1年間に26時間強。「成績」はつきません。
また、小学校にはもう一つ、紛らわしいですが「外国語科」と言う科目があり、こちらは「年間70単位時間」つまり50時間強が費やされ、「成績」がつきます。
前者は2020年、後者は2011年から必修化されていますが、いまこれらの教科に関連して全国の小学校で悲鳴が上がっています。その、具体的なお話を現場の先生からうかがいました。
この状況を打開するよう、東京大学の教員有志を中心に、全国の小学校から大学院まで教育関係者が手を携え、遅くとも2学期が始まるまでに支援策を講じることなどを、急遽決定しました。
その具体的な「悲鳴」がどのようなものか、まずご紹介しましょう。
「英語は苦手、教えたことない」担任が担当
一言でいうと、あらゆることが混乱しているのです。まず教材から見てみましょう。
文部科学省が作成した「学習指導要領対応 小学校外国語活動」教材、 3年生「Let‘s Try! 1」の「Unit3 How many?」実物を見てみましょう。
「How many?」というのだから、英語で数を数える教程だろう、と普通の人、少なくとも子供はそう思って、単元を受け始めることでしょう。
ところが、Activity②として、いきなり(本当に何の前触れもなく)
● あなたのすきな漢字を書こう。
● 友だちのすきな漢字を書こう。
とあり、「大」「数」「楽」「春」などと、イラスト化された文字が並んでいる。
「英語」の授業かと思ったら、いきなり「漢字」。
気は大丈夫か?と心配になる分裂ぶりですが、文科省の公開している「学習指導案例」を見ると「3年Unit 3-Lesson 4 How many? 数えてあそぼう 4/4時間◆数を尋ねる表現に慣れ親しみ,数を尋ねたり答えたりして伝え合う」 として
・好きな漢字や指導者の名字や名前の中から選んだ漢字を見せたうえで、「How many strokes? One, two, three … 」などと指や教師用カードを示し、漢字の画数を尋ねていることを理解させて答えを促す。
・児童の名字や名前の画数についても尋ねるなどし、最終活動への見通しをもたせる。
・児童がこれまでに学習した漢字のうち、同画の漢字を2つ3組(6字)程度選び、黒板に書く。(例)2画:人・力、4画:友・犬、8画:…等となっているのが分かります。
現場の先生からの声で、一番「困る」とクレームがあったのは「数えてあそぼう 『4/4時間』」という「4時間」という規定とのこと。
匿名で、そのまま記しますと、「あの無内容な教材で45分時間を持たせるのがまず大変」「課題は不自然で、教えている側も確信が持てない」「一番いいのは、あの教材を使わないこと」「教材は、さっさと終えたことにして、中身はALTの知恵に全面的に頼って独自に工夫」といった現実が浮かび上がってきました。
ちなみにALT(Assistant Language Teacher)とは「外国語指導助手」(教員)」で、英語の授業を補佐する外国籍の補助教員で「彼女・彼たちの工夫で何とか持っている」ところが少なくない様子が伝わってきます。
ALTは大学学部卒業が条件づけられているようですが、必ずしも教員免許は有しておらず、年間報酬は大半が336万~396万円の範囲内。
つまり、常勤教諭1人雇うよりはるかに安価な「お雇い外国人教師」頼みという、明治初期のような状態。
どうしてこういうことになるかと言えば、小学校教諭は英語を教えるようにトレーニングされていないからです。
その実、「英語が苦手だから」「英語が嫌いだから」小学校教師になったのに・・・という人もいます。
具体名は伏せますが、西日本のある県でのアンケートではそういう回答が多数を占めたと聞きました。
そして、このあたりに「英語」ではなく「外国語」、かつその「活動」などという、正体不明な科目にしてしまった原因があるようなのです。