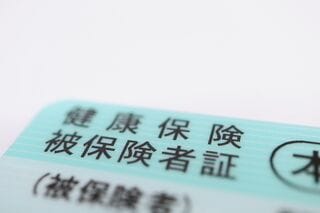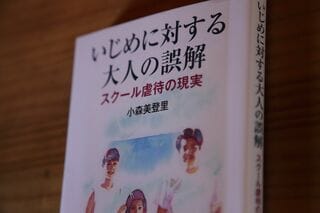九州電力川内原発=2024年6月撮影(写真:共同通信社)
九州電力川内原発=2024年6月撮影(写真:共同通信社)
九州電力が今月19日、新たに策定した経営ビジョンのなかで、原発の新設に乗り出す方針を明らかにしました。2011年3月の東日本大震災で東京電力福島第1原子力発電所が大事故を起こして以来、本格的な新設表明は日本で初めてです。政府も今年2月に閣議決定した新しいエネルギー基本計画で原発の活用を強調。福島原発の事故以降続いていた原発抑制の動きは、大きく転換し、原発回帰は鮮明になりました。果たしてこれで良いのでしょうか。「原発新設」をやさしく解説します。
九電が原発新設にカジを切った理由
九州電力が原発新設を盛り込んだのは「九電グループ経営ビジョン2035」という経営計画です。その重点目標「電源の低・脱炭素化」のなかで、「新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・設置の検討」を掲げました。「次世代革新炉の開発・設置の検討」という言葉に留めてはいるものの、原発新設の宣言です。
背景には、地域経済の盛り上がりを牽引し、同時に地球温暖化対策も着実に実行しなければならないという事情があります。
九州では、半導体製造で世界屈指の台湾企業、TSMC(台湾積体電路製造)が熊本県で半導体工場を稼働させたように、今後も半導体工場やデータセンターなどの立地が続き、旺盛な電力需要が続くと予想されています。そうした状況に対応するため、九州電力は新たな原発計画を打ち出したのです。
地元紙などの報道によると、6月に社長就任予定の西山勝取締役は、この経営ビジョンを発表した5月19日に福岡市で記者会見し、「原子力は環境問題や料金面でも大事な電源だ。(原発の新設は)まだ全く具体的ではないが、検討していくのはエネルギー事業者として必要だ」と説明しました。
九州電力は公式に認めていませんが、新しい原発の建設予定地は、1号機と2号機が稼働中の川内原発(鹿児島県薩摩川内市)の敷地内が最有力とされています。川内原発ではもともと1990年代前半に3号機を新設する計画が浮上。2000年には建設に向けた手続きも始まり、地質調査や環境アセスメントも進んでいました。ところが、2011年に東日本大震災が発生すると、当時の知事が新設計画の凍結を宣言し、現在も凍結が続いています。
つまり、新たな原発用地は、すでに川内原発の敷地内で確保された状態になっているのです。このため、今回の経営ビジョンが明らかになると、鹿児島県内では市民団体が早速、九州電力に「次世代革新炉の開発・設置」の中止を申し入れ。塩田康一知事も九州電力の経営ビジョンが発表される3日前の会見で、川内原発に対する姿勢は従来と変わらないことを強調しました。