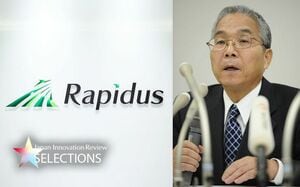小川久仁子審議官(筆者撮影)
小川久仁子審議官(筆者撮影)
前編に引き続き、個人情報保護委員会の小川久仁子・審議官のインタビューをお届けします(聞き手は筆者、木寺祥友)。
【前編から読む】
AIの活用に避けて通れない個人情報保護、世界の潮流と日本の現状
AIの急速な発展に伴い、その活用と個人情報保護のバランスが大きな課題となっています。
日本における個人情報保護法の現状と、AI開発をめぐる展望について、長年、個人情報保護問題に携わってきた小川氏の深い見解を伺いました。
小川久仁子審議官のプロフィール:1995年に旧郵政省(現総務省)入省。国際政策課統括補佐、消費者行政課企画官、電波政策課企画官、移動通信課移動通信企画官、2016年に新たに設立された第三者機関の個人情報保護委員会に出向し事務局参事官。2018年内閣官房内閣人事局内閣参事官、2020年消費者行政第二課長、2024年個人情報委員会に出向し事務局審議官(制度担当)。
検討すべき追加論点と日本発AI開発の推進
小川審議官: 今年1月に発表された今後の検討の進め方の中に、事務局ヒアリングの検討結果である4つの視点を踏まえ、短期的に検討すべき追加論点が示されています。
4つの視点を踏まえ、特に個人データの取り扱いにおける「同意規制のあり方」について、「本人の権利利益への直接的な影響」があるのかないのかを軸に規律の内容を検討しています。
1つ目は前編で述べた統計作成と整理できるAI開発を含めた場合の同意のあり方。
2つ目は一般データ保護規則(GDPR)にある「契約履行」に近い「取得の状況からみて本人の意思に反しない取扱いを実施する場合」。
3つ目は生命等の保護や公衆衛生の向上等の場合の取扱いの柔軟化です。
今まで第三者提供等は同意取得を求める等「入口」規制が原則でしたが、このように一定の条件を満たしガバナンスが確保されている場合において本人同意なき第三者提供を認めるなどの「出口」規制を可能とすることを今回ご提案しているものになります。
AI開発については、公開情報からスクレイピング(ウエブサイトから自動的に情報を収集し、必要なデータを抽出・整形する技術)して情報を集めることが一般的に行われているとされています。
公開情報からスクレイピングして取得したデータの中に要配慮個人情報が含まれる場合、同意取得が求められるものの対応が難しい場合も多いとの指摘もあります。
このようなご意見も踏まえ、統計作成または統計作成と整理できるAI開発のためだけに利用し、それ以外の目的には利用しないというガバナンスが確保されている場合について、公開情報から要配慮個人情報を取得した際の同意を不要とする案が今回提案されています。
さらに、多くのデータを持つ事業者が、別のAI開発者にデータを提供する際に、通常は個人データの第三者提供に該当し同意が必要となります。
この際、提供先が統計作成または統計作成と整理できるAI開発のためだけに利用するというガバナンスが確保されている条件の下では、第三者提供に係る同意を不要とする案が今回提示されています。
これらの提案は、かなり根本的な見直しを含んでいますが、個人の権利利益の侵害が想定されない範囲内で適正なデータ利活用の推進を図り、日本発のAI開発を推進していくべきだという強いご意見を踏まえたものとなります。
事務局ヒアリングにおいても、現在、日本語のデータが十分に集積されず、英語のデータを用いてAI開発が行われ、その結果を日本語に翻訳して利用するというケースが多く見られるという指摘がありました。
そのため、いわば「英語脳」のAIであり、日本の文化的な背景が考慮されないAIとなってしまうという指摘がありました。
例えば、3歳の子供にプレゼントするおもちゃについてAIに質問した際に、世界的に人気のおもちゃのみが提案され、日本の伝統的なおもちゃや文化に基づくものは選択肢として提案されないことにより、これらに触れる機会が失われてしまう可能性があるとの指摘がありました。
AIがこれからさらに我々の日常生活に深く浸透していく中で、英語圏の文化中心のAIが主流となっていくことは、日本の文化的背景が考慮されずに翻訳された情報だけが提供されることになる恐れもあります。
例えば、「沖縄そば」「稲庭うどん」等という多様な日本の食文化が、単に「ジャパニーズヌードル」という一つの言葉で表現されてしまう恐れもあるかもしれません。
適切なガバナンスの下で、日本語の公開データからデータを収集したり、既に保有されている個人データを事業者・組織間で共有すること等により、日本語を含む大量のデータを収集して日本発のAI開発の基盤を整備していくことは重要であると思われます。
そのためにも、個人データの取扱いがその障害にならないように制度的な検討をすることは重要であると考えています。