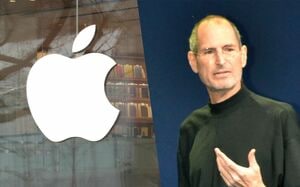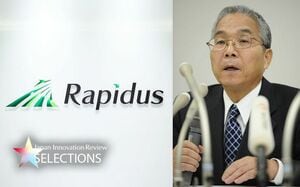平井卓也・自民党デジタル社会推進本部長(筆者撮影)
平井卓也・自民党デジタル社会推進本部長(筆者撮影)
日本におけるデジタル教育のあり方
木寺祥友:前回は、平井卓也・自民党デジタル社会推進本部長にAIの進化やロボティクス、エージェントAIの法的課題などについて幅広くうかがいました。
(前回の記事はこちらからお読みください)
今回はもう少し具体的な話題を掘り下げたいと思います。
特に私が注目しているのが、「デジタル教育」の推進です。
日本のAIやIT分野の人材不足は深刻ですが、平井先生はこの問題をどのようにお考えですか。
平井卓也:非常に重要なポイントですね。
私は以前から「デジタル教育こそ国家戦略として最優先で取り組むべき課題」だと訴えてきました。
現在の日本の教育現場では、AIやデータサイエンスの基本的なリテラシー教育が不足しています。
国際的に競争できる人材を育成するためには、小学校段階から「デジタル・AIリテラシー教育」を徹底的に実施する必要があります。
木寺:具体的にはどのような施策が必要でしょうか。
平井:まず、教師自身のデジタルリテラシーを向上させるための研修が急務です。
また、AIやデータ分析の基礎を、プログラミング教育と並行して、小中学校の必修科目として導入すべきです。
子供の頃からAIに触れさせ、親しみを持たせることで、デジタルネイティブ世代が創出されます。
この世代が社会に出る10年後、20年後の日本の競争力に直結すると考えます。
木寺:まさにその通りだと思います。実際、諸外国ではそのような取り組みが進んでいます。
では、日本でそうした取り組みを進める上での課題は何でしょうか。
平井:一番の課題は「教育現場の意識改革」です。
日本の教育は長年、知識の暗記中心型でしたが、これから求められるのは問題解決型の思考力です。
デジタル教育を通じて、クリエイティブな発想や自主的な問題解決能力を育てる必要があります。
また、産業界との連携が不足していることも課題です。
教育現場と企業が連携し、現場で使われている最新の技術を教育に反映する仕組みを作る必要があります。
木寺:企業側からも教育分野に対して積極的な関わりが求められていますね。
産官学連携を進める具体的な仕組みとしては、どのようなものが考えられますか。
平井:例えば、企業が学校現場で定期的な特別授業やワークショップを開催し、最先端技術を直接学生に紹介することが効果的です。
また、教員が企業研修を受ける制度を充実させ、教員自身が最新技術に触れる機会を増やすことも大切でしょう。
さらに、企業と教育機関が共同研究を行い、その成果を学校教育にフィードバックするという仕組みも必要です。