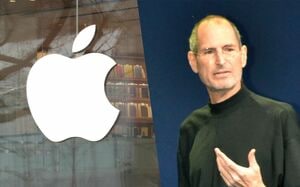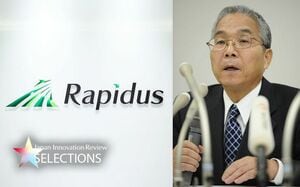講演する平井卓也・自民党デジタル社会推進本部長(筆者撮影、以下同じ)
講演する平井卓也・自民党デジタル社会推進本部長(筆者撮影、以下同じ)
2025年3月10日、一般社団法人オープンガバメント・コンソーシアム(OGC)が主催するシンポジウム「自治体DX待ったなし!デジタル活用のシナリオ」が東京・平河町の全国町村会館で開催されました。
デジタル庁や総務省、自治体関係者が登壇し、日本の自治体DXの現状と課題、今後の展望について活発な議論が行われました。
基調講演では、自民党デジタル社会推進本部長の平井卓也氏が登壇し、日本のデジタル政策の課題と未来について語りました。
本記事では、平井氏の講演内容を補足しながら、シンポジウムで浮かび上がった重要な論点を整理します。
(パネルディスカッションの内容は明日の記事でお読みになれます)
「失われた30年」と日本のDXの伸びしろ
平井氏は、日本がデジタル技術を十分に活用できていない現状について厳しく指摘しました。
「AIを部分最適化にしか使っていない。日本はいまだに労働を時間でしか計っておらず、ホワイトカラーの生産性が極端に低い」
「結果として、我々は『失われた30年』に対して根本的な改革を行わなかった」
こう述べて、日本のデジタル化の遅れが経済成長の停滞を招いたことを強調しました。
もし日本がDX(デジタルトランスフォーメーション)を適切に推進し、労働生産性を欧米並みに引き上げていた場合、「GDP(国内総生産)はすでに2000兆円を超えていた可能性がある」と指摘しました。
日本のGDPは2024年に名目で初めて600兆円を超えましたが、もし2000兆円に達していれば、1人当たりGDPも1ドル=150円として10万ドルを超えることになり、世界の高所得国の仲間入りを果たしていたことになります。
日本がその果実を手にできなかったのは、日本が技術的に立ち遅れたのではなく、改革に取り組む意志と仕組みの不備が原因であることを示唆しています。
しかし、平井氏は「伸びしろは非常に大きい」とも述べ、日本が今後デジタル政策を適切に進めれば、遅れを取り戻す可能性は十分にあると言います。