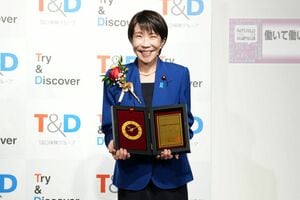写真はイメージです(出所:Pixabay)
写真はイメージです(出所:Pixabay)
心から成長を願う人がいる。周りの私たちはどう支援してあげればいいのだろうか。
米国の組織行動学の研究者たちが著した書籍『成長を支援するということ──深いつながりを築き、「ありたい姿」から変化を生むコーチングの原則』(リチャード・ボヤツィス、メルヴィン・L・スミス、エレン・ヴァン・オーステン共著、英治出版)では、成長を支援する人(コーチ)と対象者との関わり方を「誘導型のコーチング」と「思いやりのコーチング」に区別し、「思いやりのコーチング」が人の持続的な成長に寄与することを、脳科学の実験結果から明らかにしている。
「誘導型のコーチング」とは、昇進や年度目標の達成といった、外部から定められたものに向けて相手の行動変容を促すアプローチ。一方の「思いやりのコーチング」とは、相手を心から気遣って関心をもって接し、サポートや励ましを差し出し、相手が自分のビジョンや情熱の対象を自覚、追求できるようにするコーチングだ。
どうすればコーチは「誘導型のコーチング」に陥らず、「思いやりのコーチング」を実践することができるのか。「思いやりのコーチング」はどう機能するのか。そのポイントを、『成長を支援するということ』から一部を抜粋・再編集して紹介する。(JBpress、前編/全2回)
サッカーへの情熱が見られない
エミリー・シンクレアは、サッカー一家の3姉妹の末っ子だった。母親は高校と大学でサッカーをやっていたし、姉2人も同様だった。母や姉の例にならい、エミリーもサッカーチームの花形選手として高校生活を始めた。
しかしコーチはすぐに気がついた。確かに技術はすばらしいものの、コーチが長年のあいだに見てきたほかのスター選手たちのようなサッカーへの情熱が、エミリーには見られなかった。コーチが気づいたことはほかにもあった。エミリーがフィールドを走る姿は、目を見張るほど優美だった。そして驚いたことに、ほかの少女たちがいやがる練習メニューのランニングを、エミリーは心底楽しそうにこなしていた。
ある日、コーチは練習後にエミリーを呼びだし、直感のままに尋ねた。「エミリー、君はどうしてサッカーをしているのかな?」