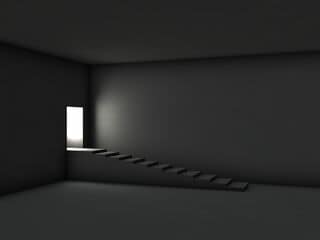2001年のカンヌ国際映画祭でのゴダール。左は女優のセシル・カンプ(写真:ロイター/アフロ)
2001年のカンヌ国際映画祭でのゴダール。左は女優のセシル・カンプ(写真:ロイター/アフロ)
今日、映画を撮ることはほとんど不可能な挑戦である。一流の映画作家でも映画を作るだけでは食っていけない。稼げないどころか製作するチャンスを見出すことさえ難しい。収益性の限界ばかりではなく、映画界がフィルムから動画の時代に移行し、映画館からストリーミングに移り、映画に人々が求めるセンスと文化も激変しているからだ。
海外で評価される芸術性の高い映画を作る監督たちは、この厳しさの中で新しい表現を生み出していかなければならない。現代において良質な映画を作るとはいかなることなのか。『映画よさようなら』(フィルムアート社)を上梓した批評家の佐々木敦氏に聞いた。(聞き手:長野光、ビデオジャーナリスト)
──昨年、映画監督の青山真治さんとジャン゠リュック・ゴダールが相次いで他界しました。ゴダールと青山さんそれぞれについて、佐々木さんが持っている印象はどのようなものですか。
佐々木敦氏(以下、佐々木):ゴダールを初めて見たのは高校生の時でした。地元・名古屋の映画館で特集上映のような形だったと記憶しています。「勝手にしやがれ」(日本公開1960年)と「気狂いピエロ」(日本公開1967年)という有名な2作が上映されて「これがゴダールか」と思った。
当時、名古屋にはまだゴダールを上映する映画館がなくて、でも、本などを通してゴダールに関する前知識が頭の中にたくさんあったので、実際に作品を初めて見た時に再確認するような感覚でした。
 「気狂いピエロ」のアンナ・カリーナ(写真:R.A./Gamma/AFLO)
「気狂いピエロ」のアンナ・カリーナ(写真:R.A./Gamma/AFLO)
ゴダールとは縁が深く、上京した後に勤めたシネ・ヴィヴァン六本木というミニシアターのこけら落とし上映はゴダールの「パッション」(日本公開1983年)でした。その次に上映されたゴダール作品は「カルメンという名の女」(日本公開1984年)。私が偏愛して繰り返し論じてきた作品です。
ゴダールは80年代に、かなり予算のかかる映画を撮っていました。それがちょうど自分が東京に出てきたタイミングと重なることもあり、ゴダールといえば、私の中では80年代の作品が中心です。
この頃のゴダールは、彼の最後を看取った、映像作家で公私のパートナーでもあるアンヌ゠マリー・ミエヴィルと一緒に「ソニマージュ工房」を設立した時期。「ソニマージュ」とはフランス語の音響(son)と映像(image)を合わせて作った造語で、映画というものは映像と音響の連鎖とその編成であるという考え方です。私の映画の見方を決定づけた視点でした。
私は映画と並行して音楽に関する評論や活動も行っていますが、ゴダール映画の中にいつも音楽的な感覚を感じてきました。