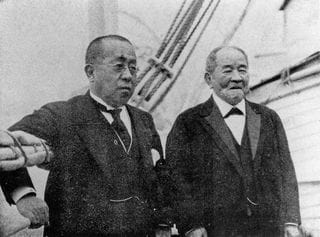食道がんステージ3から生還した男〜「切らない」という選択
『ドキュメント がん治療選択』(1)東大病院を逃げ出した理由
篠原 匡
編集者、ジャーナリスト
2021.8.7(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら