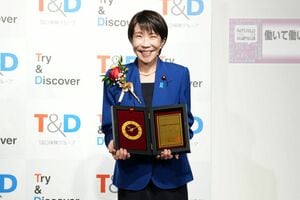(尾藤 克之:コラムニスト、明治大学サービス創新研究所研究員)
近年、社会問題化しているブラック企業。過労死、長時間労働、未払い残業代などその実態はさまざまです。しかし、その影響もあり、会社員の労働法や雇用についての知識が底上げされたように感じます。従来であれば、専門性が無ければ知り得なかった情報も入手できるようになりました。しかし、誤用している知識も多く、認識を新たにする必要があります。
最たるものが「労基署(労働基準監督署)に駆け込む」ではないでしょうか。一般的には、会社でパワハラを受けたり、退職に追い込まれたときの「駆け込み寺」として理解されていますが、実際はどうなのでしょうか。
「労基署に駆け込む」は伝家の宝刀
会社の上司や人事に「労基署に駆け込む」と言えば、まずいい顔はされません。労基署に相談したら会社との関係性が先鋭化することは避けられません。失うものも大きいのです。
労基署は、労働者の相談を何でも受けつけてくれる“駆け込み寺”ではありません。労基署は行政の組織ですし、相談料がかかるわけでもないので、勤務先との間で何かトラブルが起きると「とりあえず労基署に連絡すればどうにかしてくれる」と考えている人がいます。しかし、労基署は労基法に明記されている範囲のことしか対応しません。
労基法に明記されている範囲とは、採用における労働条件の提示、労働時間の遵守、働かせてもいい上限の労働時間と手続き、休日、有給休暇、労災保険、賃金などのことです。これらのことについて労基署は行政の立場としての助言が可能です。そして、労働者個別の事案については、労基署が介入できる範囲とは考えられていません。
個別の事案とはなんでしょうか。大まかに説明しますと、解雇妥当性の是非、パワハラや退職勧奨、嫌がらせ、セクハラ、仕事が辛いからどうにかしてほしい、などです。これらの話は範囲外なのです。まず、明確な助言は期待できません。労基署で、職員に食って掛かるような態度で接している人を見かけますが、彼らも所管する範囲外の相談には応じることができないのです。