星野リゾート卒業生が有田焼再興に奔走中
窯元も大学も心配する活発化する火山と原発再稼働
2015.5.23(土)
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら
次の記事へ
西洋の近代工業化は佐賀山中にルーツあり
あわせてお読みください
本日の新着
豊かに生きる バックナンバー

顔がない石仏、木の根が絡みつく仏頭…かつての黄金都市「アユタヤ」を象徴する文化財に修復は必要か?
髙城 千昭
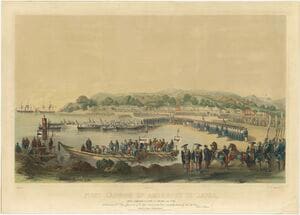
哲学者・西周が覚悟の脱藩を決めた黒船の衝撃、洋学修得へのまい進と、単なる知的好奇心ではなかった転身の本質
町田 明広

『ばけばけ』小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)の後半生、セツとの出会い、意思疎通はヘルン語、当時は珍しい帰化
鷹橋 忍

日本と韓国が「ともに生きる」ために必要なものとは?日本の敗戦から80年間の日韓関係をアートで表現する意義
川岸 徹

生産終了が迫るアルピーヌ A110と賢者の選択
大谷 達也

西洋の「模倣」から日本独自の「新しき油絵」へ…小出楢重が切り拓いた日本近代洋画の可能性
川岸 徹










