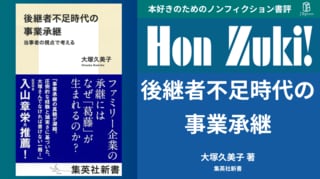都構想への反対は高齢化とパラレル
これは大阪だけの問題ではない。投票者のメディアンが60歳を超える傾向は国政選挙でも同じで、特に高齢者の多い地方の定数が多いため、高齢者が政策を決める傾向が強ま
残り1475文字
これは大阪だけの問題ではない。投票者のメディアンが60歳を超える傾向は国政選挙でも同じで、特に高齢者の多い地方の定数が多いため、高齢者が政策を決める傾向が強ま
残り1475文字
ここからは、JBpress Premium 限定です。
カンタン登録!続けて記事をお読みください。詳細はこちら