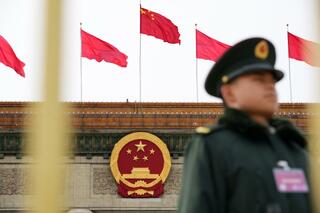「シズル感」。もし、この言葉に馴染みがないとしても、誰もが一度はシズル感に出合ったことがあるはずだ。
例えば、外食をしたとき、メニュー写真を見て、ステーキ肉の脂や赤身の色鮮やかさ、鍋から立ち上る湯気などに「ああ、おいしそう」と思いながら食べる料理を決めたことはないだろうか。この「ああ、おいしそう」と思わせる質感・雰囲気がシズル感である。肉などが焼ける音を意味する英語の「sizzle」が語源と言われており、主に広告業界で使われてきた用語だ。
シズル感の良し悪しは、客の消費動向に直結するので広告や雑誌、さらにメニューにいたるまで、あらゆる食の写真表現で重要視されている。「あ、おいしそう」と思わせるシズル感溢れる写真はどのようにして撮られるのか。
今回は、雑誌『dancyu』や、老舗和菓子店の商品撮影を手がけているプロカメラマンの相澤正さんに「シズル感」を生み出す、知られざる撮影現場について話を聞いた。
その場でできる最高の技術で撮影
高性能デジタルカメラや画像処理ソフトが普及し、撮影後の写真加工が可能となった現代だが、実はほとんどのシズル感は現場で作り出されている。特に雑誌の場合、重要視されるのが店全体の雰囲気やシェフの希望だ。
これは多くのカメラマンに共通する基本的なことだが、カメラマンは撮影前の打ち合わせで頭の中に数十種類もの撮影パターンを入れた上で撮影に臨む。撮影当日に店内の雰囲気や実際の商品を見て、食品のどこに光を当ててツヤを作るか、または影をつけるかなどの細かな点をその場で決めるのだ。
撮影時にまず確認するのは、料理の顔とも言える「正面」だ。シェフが作った料理を「その場でできる最高の技術でもっておいしく」撮影するので、この撮影時の正面は厳守しなければならない。