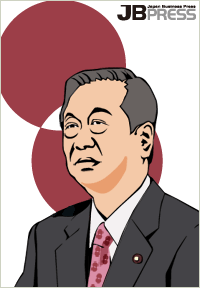「総合採算」という魔術とそのカオス
それならば長期保有目的扱いの資産は、当期利益への利益計上をあきらめればよいではないか――。そういう声が聞えてくる。全くの正論であるが、金融の現場はそれを簡単には許さない。金融機関で融資実務を経験すれば必ず聞かされる「総合採算」という魔術が、邦銀には存在するからだ。
現場では次のようなことが起きている。
融資先が無理難題の条件を提示してくる。銀行にすれば採算はどうみても赤字だ。ところが「総合採算で考えて」と稟議書に書くと、貸し出しが実行されるのだ。つまり、非常に簿価の低い融資先の株式を「政策投資株式」として保有しておき、その含み益や配当利益を貸し出しの採算と併せて考えるのである。
こうして、顧客企業とは長期にわたり信頼関係が構築される。高度成長期の株価右上がり、メインバンク制の下では実に有効かつ合理的なシステムだった。多少の貸倒引当金が発生しても、銀行は持ち株を処分することで利益を捻出し、大幅な赤字決算を避けることができた。
同時に、このビジネスモデルは金融機関によるグーループ各社の株式持ち合いを促した。このため、株主の権利行使によるガバナンス(企業統治)が機能しないと非難を浴びた。
さらに、金融機関はバブルの後始末で巨額の貸出金償却を迫られ、その原資を確保するために政策投資株の相当量を売却した。しかし、その主たる売却先は海外ファンド勢。短期的な投資姿勢を背景に株主権利行使を強行しようとすると、企業は一転して安定株主を確保したがり、銀行が保有する政策投資株の減少にブレーキが掛かった。
薄い自己資本と政策投資株、邦銀の2大リスク要因
この局面における政策投資株の保有は、以前と違って金融機関には魅力に乏しい。もはや、株価が右上がりではないからだ。簿価の高い株式を保有するから、メリットは超低金利下で相対的に高い配当だけになる。
一方、保有に至る経緯を考えれば、安定株主の地位を放棄するような売却は容易ではない。極めて流動性の低い資産である。