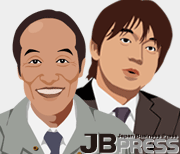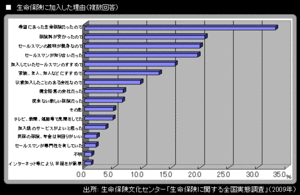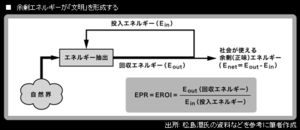もう10年以上前だろうか、ユニクロが低価格で品質の良い製品を売り出す「アパレル製造小売企業」として注目を集めるようになった頃である。柳井氏の話を聞く機会があった。そのとき彼が「ユニクロで働く人材には、年齢、性別、肌の色、国籍、出身地などの属性はまったく問わない。求めるのは、その人の能力だけだ」と言ったのを、よく覚えている。
どの経営者でも建前としては言いそうな内容である。しかし、そのきっぱりとした言い方に、建前でない決意が感じられた。世の中に顧客が求めている製品を売り出していく。そのために働く一人ひとりの能力を全開してもらう。ユニクロをそういう場にしていく。その結果として、世界をより良い方向に変えていく。そんな宣言に聞こえた。
企業は社会の公器
爆発的大ヒットとなったユニクロの「ヒートテック」と「ブラトップ」〔AFPBB News〕
実際、ユニクロの歩みはその方針に沿っている。例えば、第一線を退いた50代、60代の技術者を社員として雇用し、中国などの工場で技術指導する「匠プロジェクト」は有名だ。
障害者雇用も熱心で、全国の8割の店舗に1人以上の障害者を雇用し、雇用率も法定の1.8%を大幅に超える8%以上になっているという。さらには、爆発的ヒット商品となった発熱保温下着「ヒートテック」、ブラ付きキャミソール「ブラトップ」は女性の企画である。あらゆる歯車が見事にかみ合い、大不況の中でも史上最高益を更新している。
こうした考え方の基礎にあるのは「企業は社会の公器」という意識だろう。「社会の公器という意識を持って、お客様や社会に自分たちが提供できるもの、提供すべきものは何かを常に考える」。この柳井氏の発言は、「この会社はなんのために存在しているのか」を追求した幸之助と、発想において通底している。
読み続けられる「幸之助哲学」
世界金融危機によって不況のどん底に叩き込まれた日本経済がいつ回復するのか、いまだ霧の中だが、さて、日本企業は危機後の世界をどう予測し、それにどう対応していこうとしているのだろうか。
 没後20年経った今も、多くの人が、松下幸之助にリーダー像を求め続けている
没後20年経った今も、多くの人が、松下幸之助にリーダー像を求め続けている
米国流市場主義が流行すればそれに飛び乗り、リストラや「派遣切り」に走る。が、その「強欲さ」に批判が強まれば、ひたすら沈黙してしまう。いわゆる財界人と呼ばれる経営者たちは、自己利益だけでない別の価値観を生み出す力を持っているのだろうか。
没後20年になるというのに、幸之助の著作がいま、売れているそうだ。大型書店の経営書コーナーに行けば、平積みされているし、大手出版販売の調べでは『リーダーになる人に知っておいてほしいこと』(PHP研究所)の週間販売部数はビジネス書部門でベスト5に入っている。「儲ければ良いのではない」――。世の中全体が世界金融危機でそのことを学習したのに、日本では政治を含めリーダーたちが旧態依然だからなのだろう。