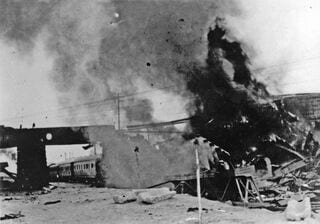天皇はコーヒーに一切口をつけなかった
二人の会談の際、マッカーサー夫人が隣室でじっと聞いていたとも言われますが、通訳の奥村勝蔵さん以外は誰も部屋にいませんでした。ところが一人だけ日本人が登場します。戦争中からアメリカ大使館に勤めていた船山貞吉さんという方で、黒紋付きの羽織袴、白足袋といういでたちで、暖炉にくべる薪をお盆にのせてうやうやしく運んだり、コーヒーのサービスをしたり、ともかく出たり入ったりしたようなんです。
その船山さんの回想によりますと、驚くべきことに、天皇はコーヒーに一切口をつけなかったそうです。もてなされたものに手をつけないのは礼を失することです。天皇のような社交的に訓練された人がそれを敢えてしたのは、敗者とはいえわが道をゆく毅然たる姿、ということになるのでしょうか。
マッカーサーもこれにはずいぶん驚いたようです。普通は口ぐらいつけるものですが、渇しても盗泉の水は飲めぬというのか、敗けても勝者の水は飲まずといったところだったかもしれません。ともかく王者の矜持というか、誇りをはっきりと見せたことになります。
以後、10回にわたる会談の際には、ついに水一杯出なかったそうで、お互い飲まず食わずで喋っていたことになります。終わると、毎回ともマッカーサーはあわててコーヒーをがぶ飲みして一息ついたと言います。
進駐軍放送から流れてきた「ヘロヘト・バウ」
この会談が写真つきで日本国民に知らされた時、さすがに皆がうーんと唸ったでしょう。内容は知りませんから、ついに軍門に下る(降参する)というか、我らが神と仰いだ天皇がマッカーサーのもとへ命乞いに行った、と悪く思った人もいたでしょう。作家、長与善郎の27日の日記にはこうあります。
「陛下は、全くただ一日も早き国土安穏ということのほか念頭になく、そのためには御自分の身も名誉も棄てていられるのだと思う。何とも云えぬ屈辱のお気持はお察しできる気がするが……」
また、日本にいながら日本からの亡命者と言ってもいい永井荷風先生(当時65歳)は、28日の日記で、めずらしく優しいことを書いています。
「我等は今日まで夢にだに日本の天子が米国の陣営に微行して和を請い罪を謝するが如き事のあり得べきを知らざりしなり。これを思えば幕府滅亡の際、将軍徳川慶喜の取り得たる態度は今日の陛下よりも遥かに名誉ありしものならずや、今日この事のここに及びし理由は何ぞや、幕府瓦解の時には幕府の家臣に身命を犠牲にせんとする真の忠臣ありしがこれに反して、昭和の現代には軍人官吏中一人の勝海舟に比すべき智勇兼備の良臣なかりしが為なるべし」
慶喜さんには、身命を犠牲にしても降伏を完結する智勇兼備の勝海舟がいた。しかし、昭和には誰一人いないのだ、と言っているのです。
私は、9月23日からはじまった進駐軍放送を、夜になると音楽やニュースなど、英語の勉強になるからと聴いていました。何日目だったか、「ヘロヘト・バウ。……ヘロヘト・バウ。……」とやたらに聞こえるので何のことだろうと思っていると、新聞に天皇・マッカーサー会見の写真が載っていたので、そうか、あれは「裕仁(ひろひと)がお辞儀をした(bow)」の意味だったのか、と思ったのを記憶しています。自分も英語がへただなあ、と。いずれにしろ、あの写真は衝撃的でした。