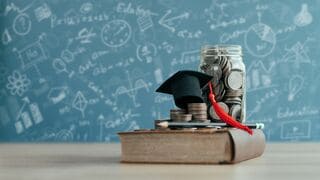授業料を上げれば大学の競争力も上がる?(写真:William Potter/Shutterstock)
授業料を上げれば大学の競争力も上がる?(写真:William Potter/Shutterstock)
- 「国立大学の学費を150万円に上げるべきだ」──。中央教育審議会・特別部会での慶應義塾長・伊藤公平氏の発言が波紋を呼んでいる。
- 国立大学が大学運営費交付金を学生1人あたり年平均230万円受け取っている状況が不健全な競争環境を生んでいるとの認識が発言の背景にある。一方、国立大学協会の永田恭介会長は6月7日、会見を開き「運営交付金は年々減り続けており、国立大学の運営はもう限界」と訴えている。
- 社会学が専門の英オックスフォード大学・苅谷剛彦教授は「授業料を上げたところで、教育の質は上がらない」と指摘する。日本ではアルバイトと就職活動による授業の中断が公然と認められているからだ。
(湯浅大輝:フリージャーナリスト)
■英オックスフォード大・苅谷剛彦教授インタビュー
(前編)日本の大学が世界で勝てない本当の理由、英オックスフォード大・苅谷教授が疑問視する「実力」
(後編)授業料3倍でも教育の質は上がらない、英オックスフォード大・苅谷教授「元凶はバイトと就活」
国立大を1カテゴリーではまとめられない
──苅谷さんは東京大学の教授とオックスフォード大学の教授を務めるなど、国内外の大学の事情に精通されています。国立大の独立法人化を含め、過去20年間の日本の高等教育政策をどのように評価しますか。
苅谷剛彦・オックスフォード大学教授(以下、敬称略):全国に86校ある国立大学を十把一絡げに捉えると、間違った認識を導いてしまうと思います。
東京大学や京都大学、あるいは10兆円ファンドの「国際卓越研究大学」の候補になっている東北大学などと、地方の国立大学の役割は明確に異なります。前者は理工系の学部を中心として、世界の大学間の競争に勝っていこうとする役割を国が期待しています。
 苅谷 剛彦(かりや・たけひこ) オックスフォード大学教授 1955年生まれ。米ノースウェスタン大学大学院博士課程修了、博士(社会学)。東京大学大学院教育学研究科助教授、同教授を経て2008年から現職。著書に『階層化日本と教育危機』『増補 教育の世紀:大衆教育社会の源流』『教育と平等』『追いついた近代 消えた近代』など
苅谷 剛彦(かりや・たけひこ) オックスフォード大学教授 1955年生まれ。米ノースウェスタン大学大学院博士課程修了、博士(社会学)。東京大学大学院教育学研究科助教授、同教授を経て2008年から現職。著書に『階層化日本と教育危機』『増補 教育の世紀:大衆教育社会の源流』『教育と平等』『追いついた近代 消えた近代』など
一方の後者は、地方出身の学生にも十分な教育機会を担保するために設立されました。例えば教員や医師の養成を目的とした国立大は、いわば国家が必要とする人材を育成するために全国津々浦々にあるのです。
つまり、地方の国立大学まで東大や京大と同じように独法化によって「稼ぐ」ことを求められるのは、無理な相談とも言えるのです。
文科省が選ぶ「国際卓越研究大学」の設立理念からも明らかですが、現在の日本の国立大学の考え方は「選択と集中」によって稼ぐ大学とそうではない大学を分けようというものです。ただ、この線引きは非常に難しい。というのは地方の国立大でも、国際的に通用する研究をしている理工系学部はたくさんあるからです。
特に、学生数が本格的に減っていく2040年以降は、財政的に厳しくなっていく私学よりも、国立大の運営方法が公的支援を受けている分だけその役割が重要になっていく可能性も大いにあるわけです。
──毎年運営交付金を減らされている中で、国立大学の財政状況も厳しくなっているのが現実だと思います。