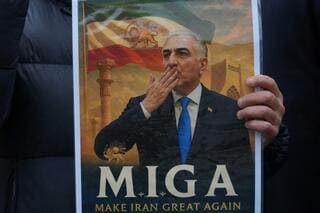気になる「社内副業」の報酬は?
そもそも「社内副業」は本業とは別で他事業部や他部署の業務に携わることであり、別に給与が支払われるといった報酬の考え方はない。あくまで給料内で本業と社内副業の時間が割り振られている。
一方で、社内副業を行うことで、新たに報酬を得られる機会をつくる企業もある。サイバーエージェントでは、エンジニアやクリエイターといった技術職を対象としたグループ内副業制度「Cycle(さいくる)」を導入。通常業務以外のプロジェクトの仕事を就業時間外に請け負うことで、報酬を得ることができる制度を構築している。
「社内副業」の評価はどうしている?
「社内副業」を採用している企業では、どのような評価制度を設けているのだろうか。ここではリコーやKDDIの事例を紹介したい。
●リコー
社員本人と直属の上司、受け入れ先責任者の3者が合意すれば、就業時間の最大20%まで他部署の業務を行うことができる「社内副業制度」を2019年4月より導入している。実施期間は原則6ヵ月以内で、副業であげた成果は人事評価にも反映される。
●KDDI
2020年6月より、就業時間の約2割を目安に他部署の業務を経験できる「社内副業制度」を導入している。社員本人、所属部署、社内副業先部署の3者が合意した上で、最大6ヵ月間社内副業を行い、社内副業先の業務も人事評価の対象にしている。
企業事例を紹介
最後に、上記であげた企業以外にも、パナソニックや丸紅が取り組む大手企業の事例を紹介する。
●パナソニック
「社外留職」と「社内複業」と呼ばれる2つの制度を導入している。「社内留職」は、従業員が提携先の出向先など他社に籍を移し、風土や価値観、経営管理手法などの異なる他社での業務を通じて、パナソニックでは得られない自己成長を促進する仕組みだ。「社内複業」では、所属部門に身を置きながら社内の新しい業務を経験し、自分の能力や可能性を試すことで自己成長を促進する狙いがある。ともに期間は約1ヵ月~1年としている。
●丸紅
「15%ルール」を同社では導入しており、勤務時間の15%を新規事業創出のための時間に充てることを可能としている。管理しないことがアイデアやイノベーションを生みやすいと捉え、時間の管理は各従業員に任せている。また、直属の上司への許可は必要なく、挑戦に対する心理的なハードルを下げるため、取り組みの報告のみとしている。
「社内副業」は従業員のキャリア形成だけでなく、企業の人材育成や人手不足といった課題の解決を支援してくれる制度といえる。一方で気をつけなければいけないのが、従業員の業務量やスケジュール管理だ。企業で導入する際や従業員が希望する場合は、業務量のバランスや頻度などを曖昧にせず、数値化したうえで「社内副業」の制度を運用していく。それが制度を円滑に進めていくうえでのポイントになるだろう。
|
著者プロフィール HRプロ編集部 採用、教育・研修、労務、人事戦略などにおける人事トレンドを発信中。押さえておきたい基本知識から、最新ニュース、対談・インタビューやお役立ち情報・セミナーレポートまで、HRプロならではの視点と情報量でお届けします。 |