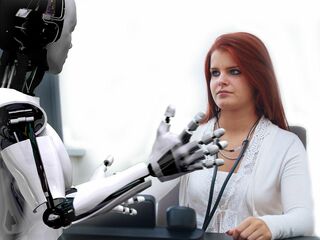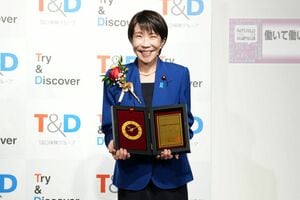生産性を追い求めると、どのような社会にたどり着くのか。
生産性を追い求めると、どのような社会にたどり着くのか。
今や、どの産業でも労働生産性を向上させることが至上命題になっている。農業でも1人当たりの生産性を上げようと、大規模化が進められている。1人が耕す面積を広げ、1人が作る農産物の量を増やし、それによって1人が稼ぐお金を増やそうというわけだ。
ところが、どの分野も労働生産性を上げようとすると奇妙なことが起きる。生産性が倍になっても売り上げは増えず、商品の単価がどんどん安くなって価格競争が延々と続き、ただ「働く仲間が減って一人孤独に必死で働いている」という状態に陥ってしまうのだ。
なぜそんなことが起きるのだろう? 「欲望が飽和しつつある」からだ。
飽和する欲望
その点、農産物は分かりやすい。日本人が1年間に食べる食糧の量は限りがある。お腹一杯でこれ以上は食べられない、という限界があるのだ。もし、その限界以上に農産物を作ってしまうと、食べられることもなく余ってしまい、いわゆる在庫となる。在庫が増えると、市場原理に基づけば価格が下落する。すると農業全体の売り上げも減ってしまうのだ。
だから農家1人当たりの生産性というか、売り上げを伸ばしたいなら、農産物の総生産量が日本人の胃袋のサイズを大きく越えないように注意しながら、農家の数を減らすしかない。つまり、農家を辞めて別の職業に移ってもらう人が出る必要があるのだ。
これと同じことをどの産業もやっている。「あなたは生産性が低いから別の産業で職を求めてね」と。
こうしてあぶれた労働力は、成長産業に移ればいい、なんてことも主張されているが、なかなかそうは問屋が卸さない。成長産業もまた、1人当たりの売り上げを伸ばそうとするから、必要以上に人を雇いたくない。つまり、どの産業にも吸収されない大量の失業者が、「生産性至上主義」社会では現れてしまうのだ。