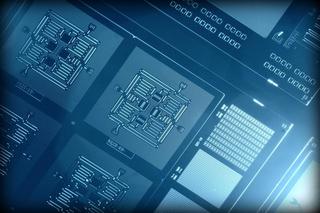国会で演説する安倍晋三首相〔AFPBB News〕
2016年6月、英国のEU離脱で為替相場は大きく動きました。結果的に円は高値をつけ、ユーロもポンドも、またドルも結果的に「とばっちり円高」の状況を呈した。言ってみれば為替の「ギアチェンジ」のようなことが起きてしまいました。
これが11月以降、米国の保護貿易・重商主義政権成立で、さらに次のギアに入ってしまい、為替は再度推移します。
一時期は1ユーロ110円近く、1ポンド130円まで漸近していた欧州通貨は、冬から各々1ユーロ120円前後、1ポンド130円程度に浮上、とは言え円高であるのは間違いありません。
国際情勢の変化、とりわけ地政的リスクである武力紛争のみならず、国民投票その他の不安定要素による迷走もまた、地政上のリスクとして考えないわけにはいかないでしょう。
ここで歴史を大きく振り返って見ましょう。
欧州、あるいは海外が経済・金融の混乱の最中にあり、結果的に発生した「とばっちり円高状態」の中で、日本はかつてどのような判断、行動を見せてきたでしょうか。
19世紀から占う2017年
時代は大きく遡ります。1880年代、西南戦争のために政府軍が購入した近代兵器によって金銀が流出し、日本はほぼ失敗国家状態に陥ってしまいました。
木戸孝允、大久保利通ら最大のブレーンが相次いで逝去するなか、新政府は松方デフレ政策などで起死回生の挽回を図りますが、まさにこの時期、欧州は19世紀世界恐慌に直撃され経済は大打撃を被りました。
その余波は露骨に日本にも押し寄せます。フランスで暴落した生糸の価格は、そのまま横浜から出荷されていた日本の養蚕農家を直撃し、富岡も高崎も熊谷も秩父もひどいことになりました。
この中で、幕藩体制期から火薬と鉄砲の伝統があった地域で、困民が蜂起したのが、人も知る「秩父事件」にほかなりません。
ちなみに私は、いま俳人の金 子兜太さんとご一緒して秩父事件の問題を考えつつ大規模な作品を作曲していますが、1つの重要なポイントがここにあります。
金子さんは封建遺制の色濃く残る20世紀前半の秩父の社会構造に問題を感じて東京帝国大学経済学部に進みます。しかし、卒業後日銀に3日間通勤しただけで南方に出征せざるを得ませんでした。
戦後も積み残されたままだった、かつて青年金子兜太が抱いた疑問を、ご一緒して考えつつ、コラボレーションを進めています。
今月は藤原書店からCDブック「存在者 金子兜太」が出ますので、その前後にまたこれについては触れたいと考えています。今回はその序論部にもあたる「松方デフレ」の周辺に光を当ててみたいと思います。