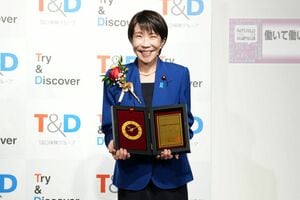大学の機能別分化を阻んでいるのは日本の社会なのか?(写真はイメージ)
大学の機能別分化を阻んでいるのは日本の社会なのか?(写真はイメージ)
日本の大学の「機能別分化」は、なぜ進まないのか。
機能別分化とは、大学がアカデミック志向の古典的大学像にのみ固執するのではなく、それぞれの分に応じた、各大学の役割を果たして棲み分けていくことを指す。中央教育審議会(中教審)はその指針として、2005年の答申「我が国の高等教育の将来像」で大学の7つの機能(役割)を提示した。
中教審が提唱してから10年以上が経ち、前回(「文系学部『廃止』騒動、文科省の真意は何だったのか」http://jbpress.ismedia.jp/articles/-/48131)触れたように、近年では文科省が相当に苛立ちを強めているにもかかわらず、機能別分化は進展していない。そして、今後も、そうやすやすとは進みそうにない。その理由を、大きく分けて3つの視点から述べてみたい。
大学教員の意識・能力が「障壁」に
第1に、現在、大学という場に職を得ている大学教員の意識と能力が、機能別分化の進展にとって「障壁」となっている可能性が高い。
今でこそ、民間企業等での一定期間の社会人経験を経て大学教員に転身する者も増えてきたが、それでも、現在の大学教員の多数派を占めるのは、大学卒業後にそのまま大学院に進学し、その後、いずれかの時点で大学に務めるようになったというアカデミック・キャリアの持ち主である。彼らの多くはまた、研究者養成を重要な任務の1つとする研究型大学の出身者でもある。
そんな彼らは、もし自らの勤務する大学が、「研究型大学」としての範疇から離脱し、特定の役割に特化して特色化を図ろうと動いた際には、その動きに戸惑いを感じ、警戒感を強めたとしても不思議はない。場合によっては、学内では“非協力(抵抗)勢力”として振る舞うかもしれない。
とりわけ、大学進学率がまだまだ低かった時代を知っている年配の教員は、かつては通用したやり方をなぜ変更しなくてはいけないのか、理解に苦しむ可能性もある。それは、教員の側の見栄といった要素だけが原因なのではない。
以前から、大学間には厳として社会的威信の差が存在していた。当然、そんなことは、誰もが理解していた。しかし、変化してしまったのは、かつてであれば、低位ランクの大学に所属していたとしても、そこでの教員は、“ミニ研究型大学”の教員のごとくに授業をし、教育をすることが許されていた(可能であった)という状況なのである。