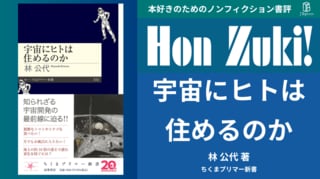国を代表する酒のことを「国酒」という。日本の国酒といえば日本酒だ。主食の米や「国菌」とよばれる麹(こうじ)菌などを使ってつくる。
30年以上前、大平正芳内閣の頃、「日本酒を国酒に」とする政府の働きかけがあった。最近でも、古川元久国家戦略大臣が日本酒を国酒に位置づける方針を示したという。
政府が方針を示すよりはるか昔から、実際、日本酒は日本の国酒であり続けた。主原料は米や麹菌。これらを使って醸造する。主食は米、気候は多湿。そうした風土がもたらした産物が日本酒だ。
歴史ある日本酒。いま、その一滴のなかに、伝統技術と現代科学の2つが溶け込んでいるのをご存じだろうか。かねて日本酒づくりでなされてきた“熟成”という段階に対して、科学的な視点からその仕組みが解明されてきているのだ。
そこで、日本酒の“温故知新”を探っていきたい。前篇では、日本酒がどのようにつくられてきたか、その歴史を追っていく。日本酒の起こりとともに、熟成に関係する製造技術として、「火入れ」という作業に焦点を当てていきたい。
後篇では、日本酒に対する先端科学を紹介したい。慶應義塾大学先端生命科学研究所は「メタボローム解析」という方法により、日本酒の熟成の仕組みを化学的に解明した。火入れ酒と生酒(なまざけ)の熟成の仕方を分析したところ、日本酒づくりに対する従来の考え方とは異なる驚くべき結果も出たという。研究所長である冨田勝教授に、日本酒を研究するという“味わい”を聞こう。
古代日本の様子を知る手がかりとなる中国の『魏志倭人伝』。ここにも日本人が「酒を嗜む」ことや、喪に際して「歌舞飲酒」することが記されている。日本人は、昔から酒を飲んでいたようだ。ただし、どのような酒をどのようにつくり飲んでいたかは、後世の文書を頼らなければならない。
飯、米麹、水を原料にして発酵させる。このような日本酒のつくり方に相通じる方法が綴られているのが、奈良時代初期に編まれた『播磨国風土記』だ。次のようなくだりがある。
<大神の御粮(かて)、枯れてかび生えき。即ち酒を醸さしめて庭酒(にわき)に献りて宴しき>
ここでの「粮」はおそらく米のこと。この粮に「かび」が生えてきた。そこで酒を醸して、神に供える「庭酒」として献じたのである。ここでの「かび」は、麹菌と考えてよいだろう。麹菌は、米の澱粉を糖に変えるという、酒造りにおいて重要な働きを持つ。