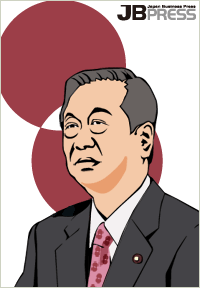鳩山政権が掲げる「政治主導」。決してそれは日本独自の概念ではない。
実は、英国はじめ先進国の政府は古くは1970年代から、政治は官僚制をどう改革していくべきかに悩み、より良い政官関係を求めて模索を続けてきた。その苦闘の歴史を「ニュー・パブリック・マネジメント」(NPM)と「政治化」という2つのキーワードで読み解いていく時、日本の周回遅れの「政治主導」の姿とその歴史的位置付けが浮かび上がってくる。
「日本の政治家は、日本の政官関係をこれから『政治化』しようとしているのですか?」
2009年秋に来日した英国のある議会関係者は日本の政治学者の説明を聞いて絶句した。そして、やおら呟いた。「ニュー・パブリック・マネジメントの導入もちょうど10年遅れでしたが、政治化も10年遅れなのですねえ」
この胡椒の利いた皮肉に対し、今度は「日本の政治主導は英国がお手本だ」と勢い込んで説明しようとしていた日本の政治学者が絶句した。
少々説明が必要だろう。
政治家と官僚の関係、すなわち政官関係はどの先進国政府でも昔から微妙な問題である。そして政官関係は政治学の主要な研究領域の1つになっている。
19世紀からロビイストが活躍するワシントン〔AFPBB News〕
かつて西欧の絶対王政の宮廷では、官僚はまず王様のための「私的使用人」であった。
他方、新大陸の新国家アメリカ合衆国では、19世紀前半に彼の地を訪れたフランス貴族アレクシス・ド・トクヴィルが感嘆したように、町の判事でさえ選挙で選ばれるほどの官僚の政治任用が進んでいた。そして大統領選の論功行賞の官職を求め、ホテルのロビーで政治家を追い回す政党関係者(「ロビイスト」の語源)も19世紀半ばにはワシントン名物となった。
ウェーバー的官僚制VSウィルソン流「政官二分論」
一体、政府の中ではどこまでが政治家の領域なのか。そして、官僚はどの部分を担当し、その採用や昇進の原理はどうあるべきか。
20世紀初め、ドイツの社会学者マックス・ウェーバーは、家産型官僚制を脱皮したヒエラルキーで手続きと権限重視の中立的官僚制こそが近代文明の担い手だと説いた。
それよりやや早く米国では、後に大統領となるプリンストン大学のウッドロウ・ウィルソン教授が、国家を代表して意思決定を行うのが政治の役割、その政治決定を実施していくのが官僚の役割だと説いていた。
このウェーバー的官僚制モデルとウィルソン流「政官二分論」は、西欧諸国からアジア・アフリカの近代化を急ぐ国へ、近代的政官関係の要諦として移植されていったのだ。
しかし、このウェーバー・ウィルソンモデルは1970年代以降、大きな試練を受けることになった。
スタグフレーションによる経済不振と相次ぐ景気刺激策の失敗により、各国の財政状況は悪化。政府機構は肥大化して機能せず、強力な労組がストを打ち続けた。この三重苦に喘いでいた国の典型が英国だった。
英国では、誇り高き高級官僚の自律性豊かな文化が中央官衙の所在地の名に因み、「ホワイトホール文化」と呼ばれていた。当時、「交通と物流がストで麻痺していても、午後3時にはお茶を悠然と飲む連中」と揶揄されたものだ。